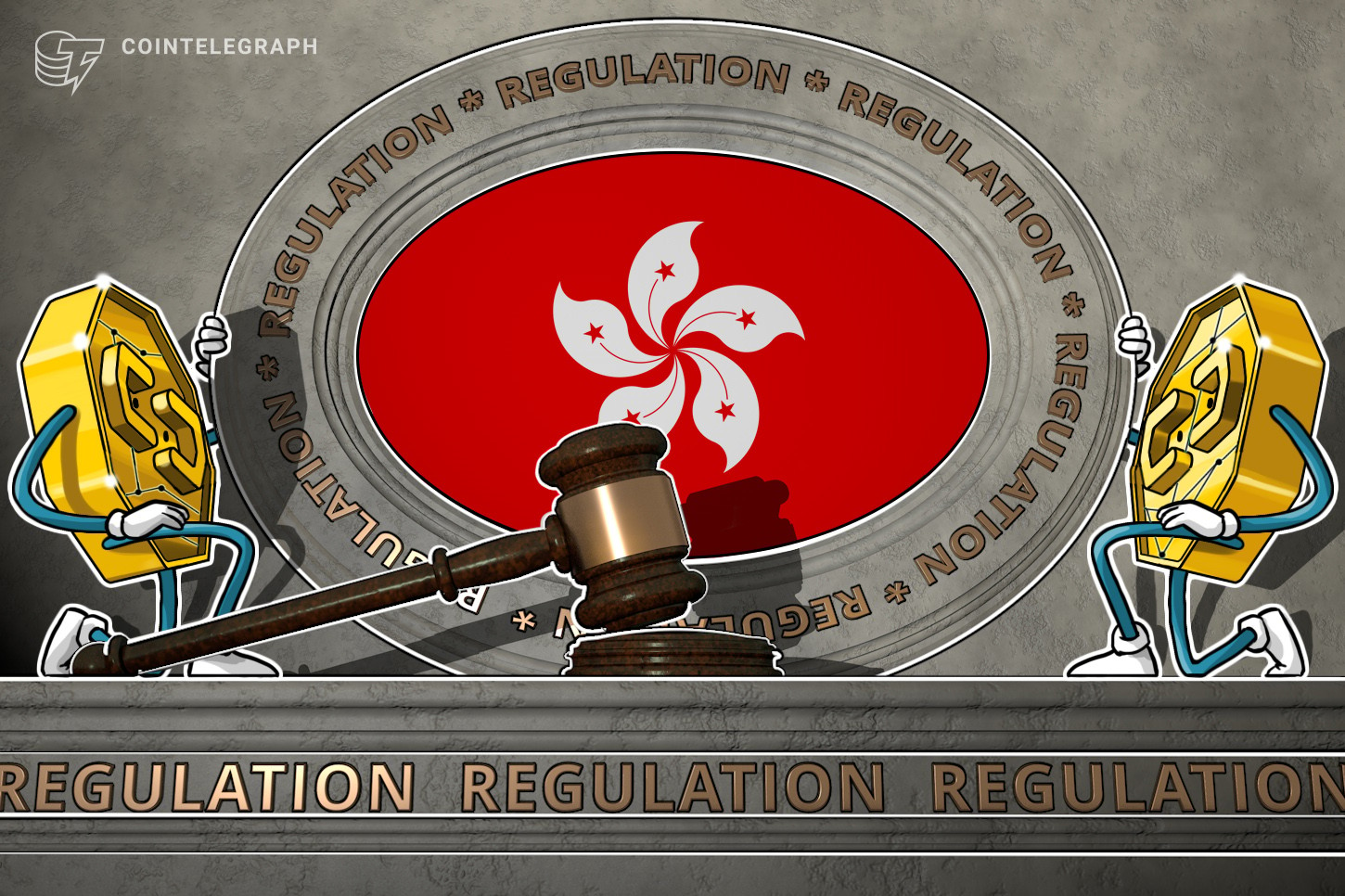香港証券先物委員会(SFC)は、仮想通貨取引所が提供するステーキングサービスに関して、新たなガイドラインを導入した。
4月7日に発表されたこのガイドラインは、ステーキングサービスを提供する取引所のほか、ステーキング資産に投資するSFC認可のファンドに対しても適用される。
SFCは声明の中で、ステーキングがブロックチェーンネットワークのセキュリティ向上や、投資家に利回りをもたらす可能性を認識していると述べ、仮想通貨取引所によるステーキングサービスの提供を認める新たな方針を示した。
香港拠点でSFC認可の仮想通貨取引所Ex.ioの共同創業者兼CEOであるチェン・ウー氏は、コインテレグラフに対し、「SFCが、明確かつ責任あるガイドラインのもとで認可取引所によるステーキングサービス提供を認めたことを歓迎している」と語った。
「この発表は、ステーキングに限らず、より幅広いWeb3プロダクトが、信頼できる規制環境のもとで形作られていく道が開かれていることを意味している」
「香港は、単なるコンプライアンス重視の市場にとどまらず、利用者の利益を損なうことなくWeb3の導入が進められる、真のハブとなることを目指している」とウー氏は付け加えた。
ステーキングサービスの新ルール
今回のルールは、SFCが管轄する仮想通貨取引所に送付した最新の通知書で伝えられた。SFCは、取引所がステーキングサービスを提供する前に書面による承認を得ること、ステーキングされた仮想資産の管理権限を維持し、第三者に管理を委託しないことを求めている。
ステーキングを行う仮想通貨取引所は、利用者に対して、手数料、最低ロックアップ期間、アンステーキングの手順、障害時対応、カストディ体制など、関連するリスクや詳細をすべて開示する必要がある。さらに、ステーキング活動に関する報告をSFCに提出しなければならない。
同様の通知書は、SFCが規制する仮想通貨ファンドの運用者にも送付されており、純資産価値の10%以上をデジタル資産に直接・間接的に投資しているファンドに新ルールが適用される。こうしたファンドは、一般公開されている仮想資産のみを取得可能であり、SFC認可のプラットフォームを通じなければならない。レバレッジによる投資は禁じられている。
ファンドがステーキングを行うには、そのファンドの投資目的に合致している必要があり、明確な開示と堅牢な統制が求められる。戦略やリスクプロファイルに重大な変更が生じる場合には、投資家への通知や株主の承認が必要となる可能性もある。
Web3を推進する香港
この発表と同日、香港Web3フェスティバルでSFCの投資商品部門エグゼクティブ・ディレクターであるクリスティーナ・チョイ氏は、「SFCは香港のWeb3推進を支援することに尽力している」と語っている。
チョイ氏は最近の講演で、Web3分野はいまだ発展途上であり、「その恩恵が本格的に顕在化するには、幾多の紆余曲折を経ることになるだろう」と指摘した。そして、非代替性トークン(NFT)の投機的なブームを例に挙げ、現在の規制アプローチに慎重さが求められる理由を語った。
「目新しさに飛びつくのではなく、我々は現実的なアプローチを取る。基盤を強化し、Web3が持続可能な形で発展できるエコシステムを育むことが重要である」
この発言は、仮想通貨取引所バイビットがNFTマーケットプレイスの閉鎖を発表したことを受けたものだ。同様に、主要なNFTマーケットプレイスX2Y2も3月下旬にサービス終了を決めている。NFT市場は急激に縮小しており、バイビットが閉鎖を発表するまでの1年間には1日あたりのNFT取引高は1800万ドルを超えていたが、発表時点では534万ドルにまで落ち込んでおり、約70%の減少である。
チョイ氏は、なぜWeb3企業が香港を本拠地とするべきかについても言及し、香港が「グローバル金融センター指数」で世界3位にランクインしていること、地元の規制当局が仮想通貨業界向けに明確な指針を設けていること、そしてアジア市場へのアクセスが容易であることを挙げた。
世界金融センター指数トップ10 Source: LongFinance
講演の締めくくりとしてチョイ氏は、「いま我々は、伝統的な金融とデジタル経済が交差し、金融市場に有望な変化をもたらそうとしている地点に立っている」と述べた。
「0から1へのブレイクスルーはすでに起きた。これからの成功は、この融合をどう育てていくか――すなわち、1から100へどう進めるかにかかっている」
こうした発言は、2022年以降で250%の成長を遂げている香港のフィンテック分野とも一致している。SFCは最近、香港を世界的な仮想通貨ハブとして位置づけるための新たなロードマップも発表した。
この「ASPIRe」ロードマップは、地域の仮想資産エコシステムを将来にわたって強化することを目指しており、市場アクセスの提供、コンプライアンスや規制枠組みの最適化、ブロックチェーン効率の向上など、5つのカテゴリーにまたがる12の施策が盛り込まれている。