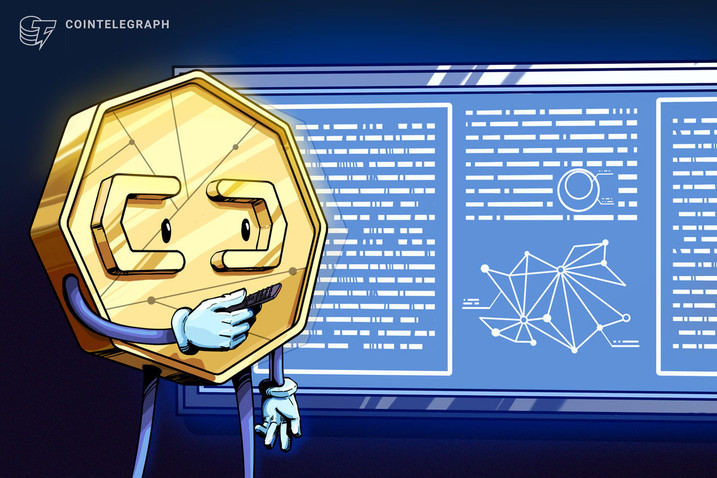スポンサーコンテンツ
火災保険は商品名に「火災」とついているので、火事の時しか支払われないお守りのようなもの。
そのようなイメージを持っている人が多いかも知れない。
ただ、火災保険は時代とともに変化しており、建物や家財に損害を受けた原因が火事ではなくその他の自然災害であっても支払う内容に進化している。
この記事では、火災保険の適用事例、申請方法や流れまで徹底的に紹介していく。火災保険の申請や見直し、新規加入を検討している方はぜひ参考にしてほしい。
火災保険とはどんなものか?
火災保険は、建物や建物内部にある動産が自然災害によって損害を受けた時、その修理代が補償される保険だ。
火災保険と呼ばれているが、保険が摘要になる要件は、火災以外にも、落雷、風、雹(表)、雪、破裂・爆発など多岐に渡る。こちらについては後ほど詳しく解説していく。
保険の対象になるものは?種類など
火災保険は一戸建ての住居以外にもマンション・アパートから倉庫、工場、施設に至るまで、建物全般、または、建物の内部に収容されている、家財、商品、設備・什器が自然災害によって損害を受けた時、その修理代を補償する。
補償の対象となることを、火災保険では「保険の対象」という。
火災保険適用に必要な条件は?
火災保険が適用となる要件として主なものを3つ紹介する。
1. 保険の目的が損害を受けた原因が自然災害であること、また不測かつ突発的事故であること
2. 保険の目的が損害を受けた原因が地震・噴火・津波でないこと
【火災保険の補償の対象外となる主な事例】
・地震が原因で火災が発生し、建物が損害を受けた場合
・地震によって建物が倒壊した
・津波が発生して建物が損害を受けた
・噴火による噴石、溶岩流、火山灰などで建物などが損害を受けた
地震・噴火・津波から保険の対象を守るためには、火災保険とは別で、地震保険に加入する必要があるので注意が必要だ。
3. 火災保険が補償内容をカバーしていること
火災保険の適用事例
火災保険は火事だけではなく、それ以外の自然災害によって建物や家財が損害を受けた場合でも補償の対象となる。火災保険の仕組みや注意点、その補償範囲について解説する。
火災保険の補償内容と補償範囲
火災保険の給付の段階で、「でる」、「でない」で揉めないためには、加入の段階で火災保険の補償内容と補償範囲、つまり「保険の対象」を明確にしておく必要がある。
建物と家財は別物
まず、建物と家財の火災保険は別物ということを知っておこう。1つ事例を紹介する。
現在、建物の火災保険に加入していて、ある日、自宅が全焼したとする。建物は火災保険に加入しているので、火事が原因であれば一般的には保険の対象になる。
しかし、建物の中にあったテレビや家具、ベッドなどの家財も焼けてしまった場合は火災保険の対象になるのだろうか?
今回の場合は、残念ながら建物の火災保険しか加入していないので、焼けてしまった家財は補償の対象にはならない。
火事になった時に、家財も補償の対象とするためには、「家財」の火災保険にも加入する必要がある。
逆に家財の火災保険しか加入しておらず、建物が全焼してしまった場合、建物は火災保険では全く補償されず、家財だけが支払いの対象になる。
建物か家財か微妙なケースがある
火災保険の保険の対象には、さまざまなものがあり、この保険の対象が家財なのか建物なのか判断につかない微妙なケースがある。わかりにくいケースについては以下の通りだ。
建物に分類されるもの
建物の基礎、浴槽、便器、調理台、門、塀、ふすまといった建具
家財に分類されるもの
家具、テレビ、冷蔵庫、パソコン、テーブル、洋服、カーテン
見分けるポイントとしては、建物に固定されていて容易に移動できないものは「建物」、容易に移動できるものが「家財」といえる。
事例を挙げると、
建物
・建物に備え付けられているエアコン
・建物に設置されている暖房は建物
家財
・コンセントだけで容易に移動できる扇風機
・簡単に移動できるポータブルストーブなど
家庭用の火災保険は、「建物」と「家財」の火災保険に両方加入することで初めて万全の備えができる。
補償内容については詳しくは以下の記事を読んで把握するのをオススメする。
火災以外での事例もある
火災保険は、火災保険以外の自然災害で建物が損害をうけても保険の支払い対象になる。損害保険料算出機構の統計によると、2018年時点で過去5年の補償内容ごとの支払保険金額は以下のようになっている。
火災、落雷、破裂・爆発
2014年〜2018年平均支払い額:385億円
自然災害
2014年〜2018年平均支払い額:2,122億円
その他(水濡れ損害)
2014年〜2018年平均支払い額:527億円
火災についてのみの支払保険金額は統計からは確認できないが、少なくとも火災以外の自然災害やその他事故の方が圧倒的に保険会社の保険金支払い額が大きいことがわかっていただけるだろう。
なお2018年は大型台風が数回発生し、各保険会社で多くの保険金支払いがあったため大きな数字が発生して平均支払額を押し上げている。
関連記事:火災保険で台風被害の請求が出来るってホント?知らなかった火災保険の補償内容
増加する水濡れ事故
近年特に増加している代表的な事故に水濡れがある。増加している事例としては、ピンホールという事故だ。
おおよそ15年位以上経過した物件でよく発生する現象で、老朽化により水道管の内部が腐食するとピットという小さな穴があくことがある。
このピットから水漏れが発生し、壁や天井にシミができる(破汚損(はおそん))という事故が急増している。一見、経年劣化が原因とした損害に見えますが、ピンホールに関しては支払いの対象としているケースが多いようだ。このケースは、給排水の損傷個所は火災保険の対象にはならないが、天井や壁の張替え費用は対象になる。
ただし、保険会社によって見解が異なる可能性もあるので、都度確認してほしい。
火災保険の驚きの支給事例集
その他、少々珍しい火災保険の給付事例を紹介する。保険会社によって見解が異なる場合や、現在加入している火災保険は、不測かつ突発的事故は補償の対象外として契約している場合もあるので個別の案件に関しては必ず保険会社に相談してください。
自分の車で自宅の建物を破損させてしまった。
この場合、車の修理代金は自動車保険の対象になるが、建物の修理代は一部保険会社で支払いの対象になる。
風でアンテナが倒れた
風によってアンテナが倒れた場合、アンテナの修理代は建物の火災保険で風災の事故として支払われる。また、アンテナが倒れて建物に損害を与えた場合も風災として支給の対象になる。
強風で雨どいが破損した
風や大雨で雨どいが破損した、または外れてしまった場合も風災として支給の対象となる。
子どもが室内でボールを投げてガラスを割ってしまった
この場合も不測かつ突発的事故が原因として火災保険の支給対象となる。ただし、不測かつ突発的な事故は、多少の自己負担が必要となる保険会社がほとんどだ。
火災保険の時効
ここまで解説してきたように、火災保険は火事以外でもさまざまな要因が支給の対象になる。もしかしたら、あとから昔の事故が火災保険の対象になったかも?と気が付くことがあるかも知れない。
火災保険は保険法第95条において、保険金請求する権利は事故発生から3年以内と定められている。
したがって、火災保険の請求を忘れていても3年以内であれば保険会社に請求すれば、受付してくれる。
ただし、年月が経過すると事故と損害の因果関係を証明することが難しくなる。すでに修理をしてしまい、写真も見積もりも何も残っていないという場合は、さすがに請求しても受け付けてもらえない。
火災保険は、速やかに請求することが一番ですが、後から火災保険の対象となることを知って、見積もりは事故写真がこのっている場合や、まだ請求していない場合は、忘れずに火災保険の保険金請求しよう。
火災保険金の申請・請求の方法
誰でも事故が起こった場合、すぐに給付の対象になるかどうか知りたいところだが、保険会社は全ての書類がそろってから給付の可否判断する。
保険金請求の流れは以下の通りだ。
1. 損害箇所の特定・撮影
実際に事故があったことを証明するために、損傷個所を写真に撮る(近年ではデータで送ることも可能なので、スマホで撮影しても問題ない。
できれば、撮影は危険な場所もあるうえ、請求のポイントをおさえた写真撮影してくれる業者にお任せするのをオススメする。
ただし、近年火災保険を利用した、悪質な修理サービス業者によるトラブルが増えている。
無料で損害調査を請け負いますとアプローチし、「屋根瓦が破損している」や「建物の一部が劣化している」などと言い、「火災保険を使用し、自己負担がなく修理できる」と偽り、先に高額な修理代を徴収する悪質なものだ。
関連記事:火災保険申請サポートは詐欺?違法性や実際のトラブルや怪しいかを徹底調査。詐欺に引っかからないための自己防衛方法。火災保険の申請代行には要注意!
火災保険申請サポートに調査をお願いすると、素人では見つけられない細かい損害を見つけてくれ、自身で調査するよりも多く保険金を受け取れるケースなどもある。
また、先述した通り、自身で調査する場合は屋根に登る必要もあり、足を踏み外して思わぬ怪我につながる場合がある。
そのため、申請サポートに頼むメリットはあるが、怪しい・詐欺まがいな業者も多いため、完全成果報酬で実施してくれる申請サポート事業者を探すのを推奨する。
屋根に登って損害がないのに、意図的に壊されて保険金申請するトラブルもよくあるため、極力屋根に上らせないほうがよい。
JAPAN損害調査サービスではドローンを使って損害調査するため、調査員を屋根に登らせる必要がなく、意図的に屋根を壊される心配もない。しかも立会いも不要なため、調査員と接触する必要もなく感染症対策の面でも安心だ。
ドローンで調査している申請サポート会社は珍しいため、気になる方はまずは申し込みしてみるのを推奨する。
申し込み後に電話がかかってくるのでその場で状況を伝えて、お互い確認した上で調査に進めるので安心だ。
2. 被害額の見積もり作成・提出
JAPAN損害調査サービスでは損害箇所の特定・撮影および見積もり作成も行ってくれる。この段階では、まだ火災保険が給付になるかわからす、修理にも取り掛かからない。
ただし、保険が出る、出ないにかかわらず修理する場合は火災保険金の給付を待たずに修理してしまっても問題はない。
3. 保険会社と保険加入者がやりとりする
その後、保険会社から火災保険金の請求書類が送られてくる。必要事項に記入し、写真、見積もりを同封して保険会社に返送する。(データの場合はプリントアウトするか、所定のメールアドレスに送付)
保険会社から支給の可否の連絡が来る。保険金が支給されることが決まれば、おおよそ1週間くらいで保険金が指定の口座に振り込まれる。なお、修理業者に直接保険金を支払うことも可能だ。
火災保険の給付金の使い道とは?修理代?
支払われた火災保険金は、損害箇所を修理することで発生する経済的損失を補うためのものだが、受け取った火災保険金は、必ずしも修理に使わなくても問題ない。
ただし、当然だが、該当する損傷個所の修理代として保険会社は保険金を給付している。そこを修理せず、損傷個所が拡大してしまった場合、今後、保険会社は支払いに応じてはくれないので注意が必要だ。
もちろん過去に損害申請した箇所と全く因果関係のない損害であれば補償の対象になる。
賃貸アパートの火災保険は加入する必要はある?
賃貸アパートの火災保険は何のために加入するのか?と疑問に思う方も多いようだが、結論から言うと賃貸アパートの火災保険は加入必須だ。
賃貸アパートの火災保険の中身をよく見てみると、主な契約内容は「家財の火災保険」であることがわかる。なぜなら賃貸アパートの建物の持ち主はアパートの大家になので、入居者は建物の火災保険に加入する必要がないからだ。
そうなると、もし火事になって自分の家財が焼けたとしても、その時は買いなおせばいいから、賃貸の火災保険には加入しなくてもいい。と考えてしまう人もいるかも知れない。
しかし、賃貸アパートの火災保険に加入する本当の目的は、家財の火災保険に備えるためではない。
賃貸の火災保険は主に以下の3つのパートで構成されています。
1. 家財の火災保険
2. 大家への賠償責任保険※2)
3. 他の入居者への賠償責任保険
※2)賠償責任とは相手に対して弁償する責任があるということで、弁償するために支払った代金を補償する保険のことを賠償責任保険といいます。
家財の火災保険については、先に述べたとおりなので、ここでは大家への賠償責任保険と、他の入居者への火災保険について詳しく解説していきます。
大家への賠償責任保険
大家への賠償責任保険は、正式名は借家人(しゃっかにん)賠償責任保険といい、家財の火災保険の特約として加入する。
入居者の行為が原因で部屋に火事が発生した場合、家財も損害を受けるが、部屋も壁や床が焦げたり、損傷を受けたりする可能性がある。建物の持ち主は大家なので、建物の火災保険に加入するのは大家だ。
しかし、入居者の責任で火災が発生したにもかかわらず、大家の火災保険で保険金請求の手続きする必要があるのだろうか?入居者の責任で事故が発生した場合は、入居者が責任をとるのが通常だ。
そんな時に必要になってくるのが借家人賠償責任保険特約だ。入居者の責任で、建物に損害を与えた場合、大家に対しての賠償責任保険金を支払うのがこの特約の役割だ。
実は、賃貸アパートの火災保険の最も重要なパートはこの借家人賠償責任特約なのだ。
近年は、火災保険の給付額が増加して保険会社の収益を圧迫している。
そのため、何度も同じ物件で保険の給付が発生している場合は、改善を促す意味で火災保険の更改させてもらえない。保険料を上昇させる。自己負担(免責額)を増額したりする。などの措置をとる傾向が高まっている。
火災保険は自動車保険のように従来は使っても、保険料が次年度に上昇するということはなかった。現在も使ったからといって基本的には保険料が上昇することはないが、個別に特別条件として、高い保険料を払うことを条件に火災保険の更改を認めるとするケースが増えている。
保険会社がこのようなスタンスにある以上、今後、大家は入居者が自分の部屋で起こしたトラブルは自身で解決してもらうよう、ますます入居者の火災保険の加入を強くすすめる傾向は高まってくるだろう。
賃貸アパートの火災保険は、基本的に2年に1回更新で、ほったらかしにすると更新を怠る入居者が一定数現れる。定期的に大家は入居者に火災保険の加入状況を確認しているケースも増えているようだ。
他の入居者への賠償責任保険
入居者が迷惑かけるのは大家だけではない。
例えば、外出している間に洗濯機のホースが外れて水漏れしてしまい、下の階に住んでいる入居者に損害を与えてしまうことがある。
他の入居者に迷惑かけた場合は、借家人賠償責任保険特約では補償の対象にはならない。他の入居者への賠償責任保険金をカバーするには個人賠償責任特約(または日常生活賠償責任特約)に加入する必要がある。
自分の部屋と下の階との間には共用部分があり、水漏れによって共用部分の断熱材の交換が必要になるケースもあるため、借家人賠償責任保険と、個人賠償責任保険の両方がないとこの場合、すべての賠償責任をカバーできない可能性がある。
賃貸アパートの火災保険は、内容だけみると主に自分の家財の火災保険がメインの内容となの為、つい軽く考えてしまいがちだ。
しかし、賃貸アパートの火災保険のメインは、借家人賠償責任特約と個人賠償責任特約であるというのを心得ておこう。
火災保険は値上がり傾向
2018年の台風の影響により、膨大な保険金の給付が発生したことや、老朽化した物件が増え水濡れ事故が増加していることにともなって、火災保険料と、地震保険料も値上がり傾向だ。
火災保険は住んでいる人が引っ越ししたり、家を建て替えたりするため、定期的に補償内容の継続の意思を保険会社に伝えなければならない。これを火災保険の契約の更改というが、更改する時は、その時点での保険料で更新することになる。
全てのケースが一律に保険料は上昇しているわけではなく、築年数が経過している物件や、築年数が不明な物件については保険料が特に上昇している傾向がある。
そのため、保険料が著しく上昇するため、補償範囲を減らしたり、保険金額を減らしたり、家財の補償の更新をストップしたりと火災保険の補償を下げるケースが増加している。
しかし、保険会社は、火災保険をいたずらに上昇させているわけではなく、適正な根拠に基づいて保険料を算出している。火災保険料が上昇しているということは、誰もが火災保険を使うリスクが高まっていると考えられる。
火災保険の補償範囲を見直す事例としては、水災を見直すケースが多くみられる。
水災の場合は自治体で、ハザードマップ(https://disaportal.gsi.go.jp/)を無料で配布しており、大雨や台風が発生した場合、自分の住んでいる地域で河川の氾濫などが発生する可能性はどれくらいか?が色付けされていて、一目で簡単に確認できる。
ハザードマップを確認して見直せば100%安心というものではないが、補償範囲の見直しはしっかりと根拠を持ったうえで、慎重に行ってほしい。
保険期間も最長5年に見直しの方針
現在、火災保険は最長10年間加入できる。しかし、災害リスクが高まり、保険会社が先々のリスクを見通しづらくなっていることから、長期の火災保険契約を見直す傾向がある。現在の加入期間は10年だが、近い将来、5年契約が最長になっていく見通しだ。
まとめ
火災保険は建物や家財が火事で損害を受けた時のみ、補償するわけではなく、その他多くの自然災害が原因でも支払いの対象になる。
統計では、火事原因としたものよりも、それ以外の自然災害を原因とした給付額の方が多い傾向がある。
補償範囲は、ある程度自分で決められるが、ハザードマップなどの公的資料をもとに慎重に検討しよう。
賃貸アパートの火災保険は、同じ火災保険でも目的が一戸建ての火災保険とは全く性質が違うものだ。しかし、いざという時に加入をしてないと大きな自己負担が発生する可能性が高いので、必ず加入しよう。
自然災害が増えており、各保険会社ともに保険金の支払いが増加している。そのため、保険料も上昇傾向だが、やみくもに補償を落とすのではなく、それだけ必要性が高まっていると考え、しっかり火災保険を検討し、自分の資産を守っていこう。
無料の損害調査や見積もり作成に、必ず押さえておきたい火災保険申請サポート会社
JAPAN損害調査サービス:ドローンで調査のため、調査員を屋根に登らせずに調査可能。年間1,200件以上の調査実績があり、平均135万円の給付実績あり。
✔︎今なら調査完了でもれなく全員3,000円分のamazonギフト券プレゼント中!
関連記事:火災保険の申請サポート会社のおすすめ比較ランキング!手数料や給付事例など、詐欺ではない信頼おける法人を紹介
免責事項。本コンテンツは有料パートナーシップの一部です。以下のテキストはスポンサー記事であり、Cointelegraph.com の編集コンテンツの一部ではありません。本資料は当社のアドバトリアルチームによって作成され、明確性および関連性を確保するために編集上のレビューを受けていますが、Cointelegraph.com の見解や意見を反映していない場合があります。読者は、当該企業に関連する行動を取る前にご自身で調査を行うことが推奨されます。 開示.