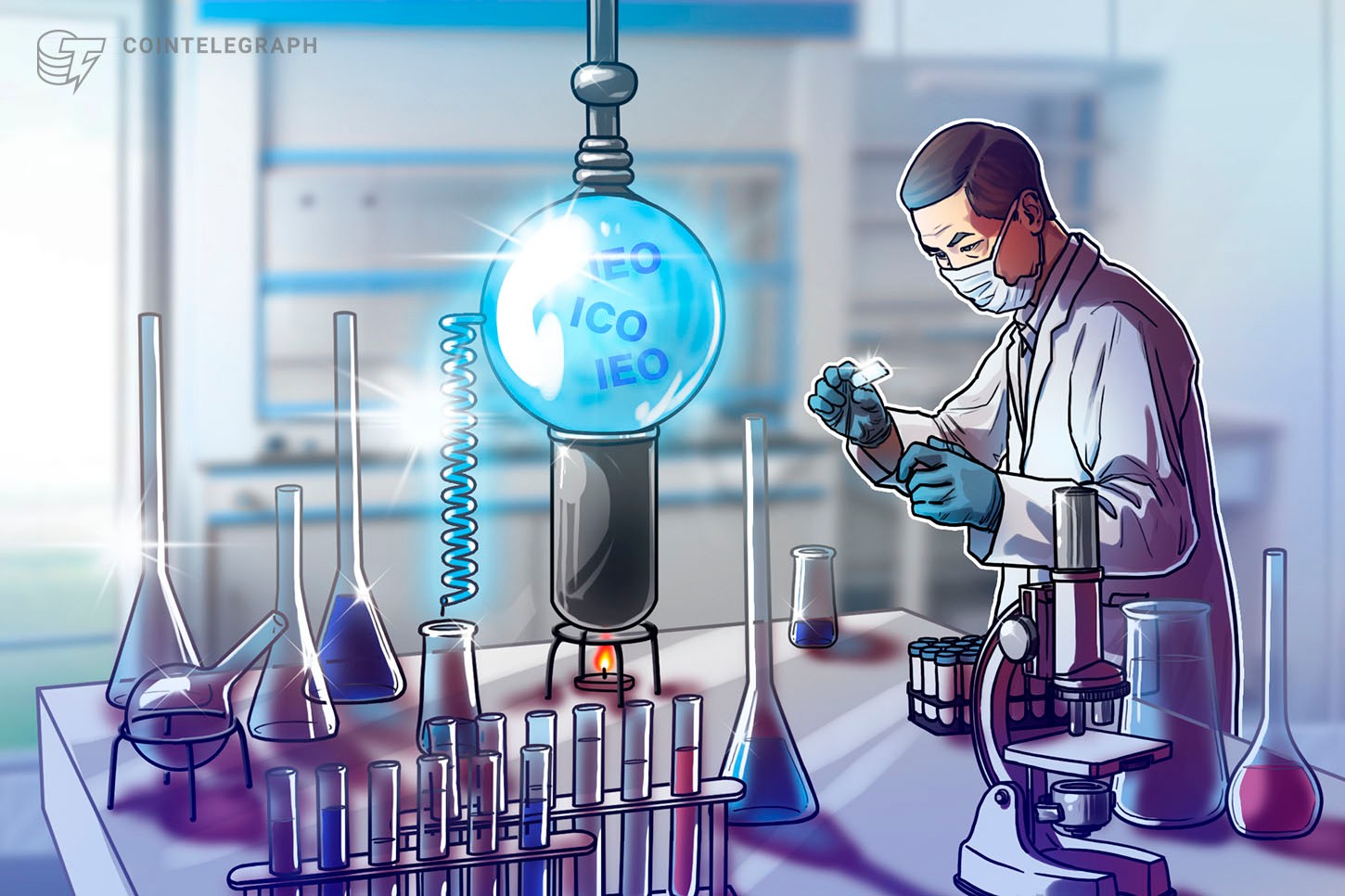仮想通貨交換業の自主規制組織「日本仮想通貨交換業協会(JVCEA)」が9月27日、新規仮想通貨に関する自主規制規則を公表した。これにより、いわゆるICO/IEOでも、日本でのルールが明確となった形だ。
今回の自主規制ルール整備によって、国内のICO/IEOへの影響はどうなるのか。専門家や国内の取引所に聞いた。
「手詰まり感は解消」
ICOに関する著作もある法律事務所ZeLoの小笠原匡隆弁護士は、「『とりあえず、一旦はICO及びIEOは待って』という状況だったが、その点の手詰まり感が解消された」と評価する。
小笠原氏は、今回の自主規制ルールをもとに、実勢にICO/IEOの国内事例が積み上げられていくことで「透明性が増していくだろう」と語る。
「今後はJVCEAの審査基準に基づいて、ICO及びIEOの審査がなされるとともに、実務的にも前例が重なりよりICO及びIEOを実施するにあたっての環境は透明性を増すものと考えられる」
今回の自主規制規則では、ICOの実施者に対して「実現可能性」の審査や四半期ごとの情報開示を求める内容となっているが、小笠原氏は「必要十分な内容であり、ICO及びIEOを実施する主体や、ブロックチェーン業界全体として見てもポジティブな内容だ」と話す。
実際、ICOやIEOの界隈では「詐欺的な案件を耳することも多かった」(小笠原氏)。その点からも「情報の透明性については非常に重要」と、小笠原氏は強調する。
「昨年より、極めて多数のICO及びIEO案件のアドバイザーを務める中で数々の詐欺的な案件を耳にすることも多かったため、情報の透明性については非常に重要であると考えられる。この点を担保した今回の自主規制ルールは評価できるものと考える」
スタートアップにも一定の配慮
今回の自主規制規則では、前述のとおり、ICOの実行者は購入者に実現可能性を説明し、詳細な情報開示を行わなければならない。今までのホワイトぺーパーだけを出してお手軽に資金調達というわけにはいかなくなる。
ICOはスタートアップにとって、ベンチャーキャピタル(VC)に代わる新しい資金調達として注目されたが、今後国内のスタートアップにとって国内ICOは選択肢に入るのだろうか。
小笠原氏は、シード期のスタートアップでも、プロダクトが完成しているなどの条件がそろえば、利用可能性はあるとみる。
「シード期のコンセプトのみのスタートアップが利用するのは極めて困難であると考えてはいるものの、シード期であっても、ファイナンスを受け、プロダクトが完成している等のフェーズまで進んでいれば、利用可能性はある」
実際、JVCEAのガイドラインの中では「発行者の規模、業容、成長フェーズ…等を考慮した個別具体的な評価・判断が妨げられるものではない」とされているが、小笠原氏によれば、パブリックコメントへのJVCEAの回答を見ても「その点は改めて明確化されている」。「JVCEAも、スタートアップによるICO又はIEOによる有益なトークンエコノミーの形成を阻害する意図はないものと考えられる」(小笠原氏)
では実際にスタートアップの「実現可能性」は、どのように評価されることになるのか。
小笠原氏は、既にトークンを付与し、ユーザーコミュニティがしっかりと育っているようなプロジェクトといったケースで「上場」が認められるのではないかと分析する。
「例えば、スタートアップであっても、既にトークンがユーザーに付与されており、その意義が一定程度のユーザーから認知されており、不必要に多額の資金を調達することを目的としないプロジェクト等については、当該トークンのリスティングについて、『実現可能性等』は認められやすいものと考える」
国内取引所「大きな進展」
今年8月にIEO事業の検討を開始したコインチェックは、今回の自主規制を「大きな進展」と評価する。今後、IEOを具体化していくためには、情報開示や審査項目の整理が必要との認識も示した。
「事業を具体的に進めていく上では、情報開示や審査項目などにおいてまだ整理が必要な部分も一部あると考えている。それについては、JVCEAや発行体となる企業と連携しながら事業化に向けて検討を進めていきたい」
今年8月の発表では、コインチェックではユーティリティトークンによる資金調達を支援していく考えだ。トークンを活用した資金調達を行っていない企業やプロジェクトで、既にコンテンツを持ち、ユーザーコミュニティ拡大や事業成長を目指すものをターゲットにしていくとしている。
利用するプロジェクトは「なかなかない」
別の国内取引所関係者は、今回の自主規制について「投資家にとってはメリット」と評価する一方、「日本でIEOをしたいというプロジェクトがなかなかないのが現状」と話す。
17年に活発だったICOも18年、19年と調達額は減少傾向だ。「ベンチャーキャピタルの代替として注目を集めたが、現状はとてもそんな状況ではない」(取引所関係者)という。
「今後、国内のプロジェクトがどういう反応なのか見ていく必要はあるが、活用する企業は上場会社などに限られるかもしれない」
また日本のプロジェクトであっても、バイナンスなど海外のプラットフォームを選択肢にする可能性があると指摘する。
「自社トークン買い」など整理必要
小笠原氏に今後の整理が必要な部分についての評価を聞くと、「あえてあるとすれば、『自社トークン買い』について情報開示の対象とすることが考えられる」と指摘する。
自社トークン買いは、自社が自社のトークンを買い取る行為。株式の世界での「自社株買い」のようなものだ。仮想通貨取引所バイナンスや国内では分散型ソーシャルメディアのALISが行っている「バーン(Burn)」のような仮想通貨の償却に付随して行われることがある。
実際、株式の世界で自社株買いをする場合には情報開示をしているが、トークンの場合でも開示をすることで購入者への透明性が高まるだろうと、小笠原氏は語る。
「『自社トークン買い』を行うとトークンの価格が安定することが多い。これを行う場合には、自社トークンの償却の開示とは別に、予めユーザーに当該情報を開示しておいた方が、情報の透明性が確保されるため、開示対象とすることが考えられる」
アジアのモデルケースになる可能性
国内取引所関係者からは、今回の自主規制がシンガポールなど海外の自主規制のモデルケースになる可能性があるとの声も出ている。
シンガポールでは、仮想通貨企業の業界団体「仮想通貨企業・スタートアップ協会(ACCESS)」が、アンチマネーロダンリグ(AML)規制を策定するなど、自主規制を策定する動きが進んでいる。
取引所関係者は、今後アジア各国で業界による自主規制が作られる中、「シンガポールをはじめとする国々が、今回の日本の規制に追随していく可能性がある」と分析している。