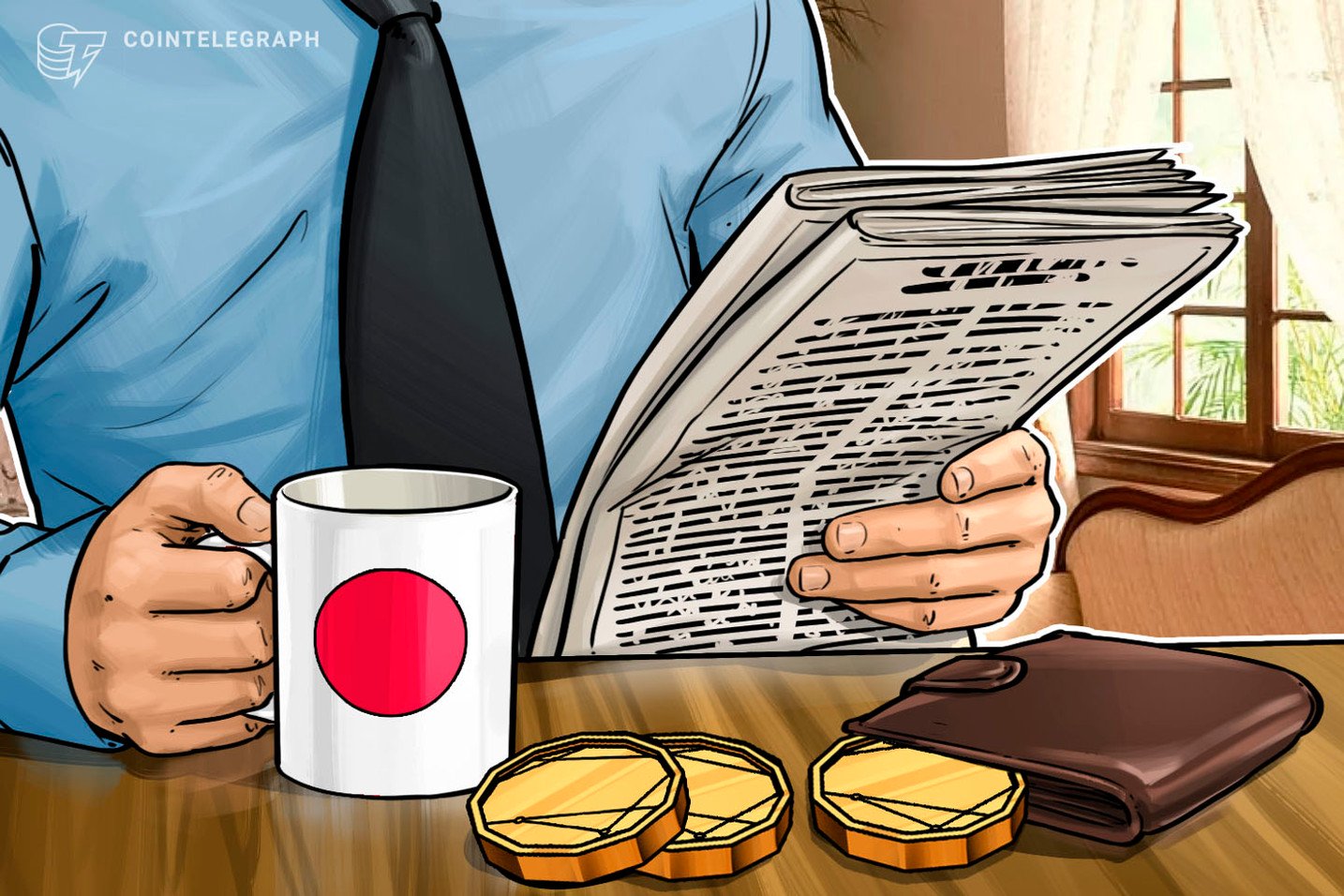日本暗号資産取引業協会(JVCEA)と日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)は7月31日、「2021年度税制改正に関する要望書」を取りまとめたと発表した。両者は昨年、税制改正に関する要望書をそれぞれ提出していたが、今年は共同で提出し、業界全体が持つ懸念をさらに強いものとして訴える狙いがあるようだ。
今回の要望書では、以下の課題を指摘した。
「我が国は、ブロックチェーン技術の将来性に確証が持てないとして、国家としてブロックチェーン戦略を打ち立てることができておらず、インターネットにおいて取り戻せないほどの後塵を拝した過ちを繰り返そうとしているが、現状の暗号資産に関する税制もまた、我が国が将来得られる可能性がある戦略的に優位な地位を毀損する内容となっていると思料する。」
そのために、「暗号資産の決済における利用促進、市場の活性化、関連産業の発展」を目的とするとして、仮想通貨(暗号資産)税制について以下の点を要望した。内容については昨年提案したものと変わらず、20%の申告分離課税導入を強く訴えた。
(1)暗号資産のデリバティブ取引について、20%の申告分離課税とし、損失については翌年以降3年間、デリバティブ取引に係る所得金額から繰越控除ができることを要望する。
(2)暗号資産取引にかかる利益への課税方法は、20%の申告分離課税とし、損失については翌年以降3年間、暗号資産に係る所得金額から繰越控除ができることとする。
(3)暗号資産取引にかかる利益年間20万円内の少額非課税制度を導入する。
株式や投資信託、FXのように20%の分離課税とは異なり、現在の仮想通貨の取引益に関する税制は最高税率55%の総合課税となっていることが大きな業界課題となっている。
(1)について今回は特に、5月に施行された改正資金決済法や改正金融商品取引法の内容を踏まえ、「暗号資産につき、金融資産性をもつ支払手段という複合的な性質をもつことが明確化された」など、仮想通貨が支払い手段としての性質だけでなく、金融資産の性質が認められたことを受けて、仮想通貨デリバティブ取引などをそのほかの金融商品と同等の扱いを求めた。
また仮想通貨は取引損を翌年以降に繰り越すことも認められていない。例えば今年大きな損失が出したが翌年に利益を出した場合に、通算の損益はマイナスであったとしても、多額の税金を納めなければならない状況になっている。しかし、株式や投資信託、FXなどは損失を繰越すことが可能だ。こうした繰越控除についても株式などと同様の制度改革を求めた。
(2)については、仮想通貨でモノやサービスを購入した場合では現状、含み益があれば課税される。決済のたびにその都度、損益計算をすることは非常に煩雑になる。また、仮にビットコインでイーサリアムを購入した場合にも、その都度損益計算をし、利益が出た場合には納税の必要がある。その都度計算する作業は非常に煩雑なため、取引量増加の大きな足かせとなっている。
(3)の少額非課税制度の要望も社会の中で仮想通貨が使われるようになるために重要だ。現在の税制では仮想通貨を使った決済が課税対象となっている。これが少額でも課税されるのが問題なのは、例えば5000円分の買い物をビットコインで支払った場合に、その時点でのビットコイン価格とビットコインの購入価格から損益を確定し、利益が出ていたら納税しなければいけないということだ。都度こうした作業が発生していたら、利用は非常に複雑になる。そのため、一定の決済については非課税としなければ、実社会での利用拡大は見込めないだろう。
こうした要望は前参議院議員の藤巻健史氏も昨年、税制改正の嘆願書を国会に提出。現在の国会議員では音喜多駿議員(日本維新の会)が仮想通貨税制に関する質疑を行なっている。