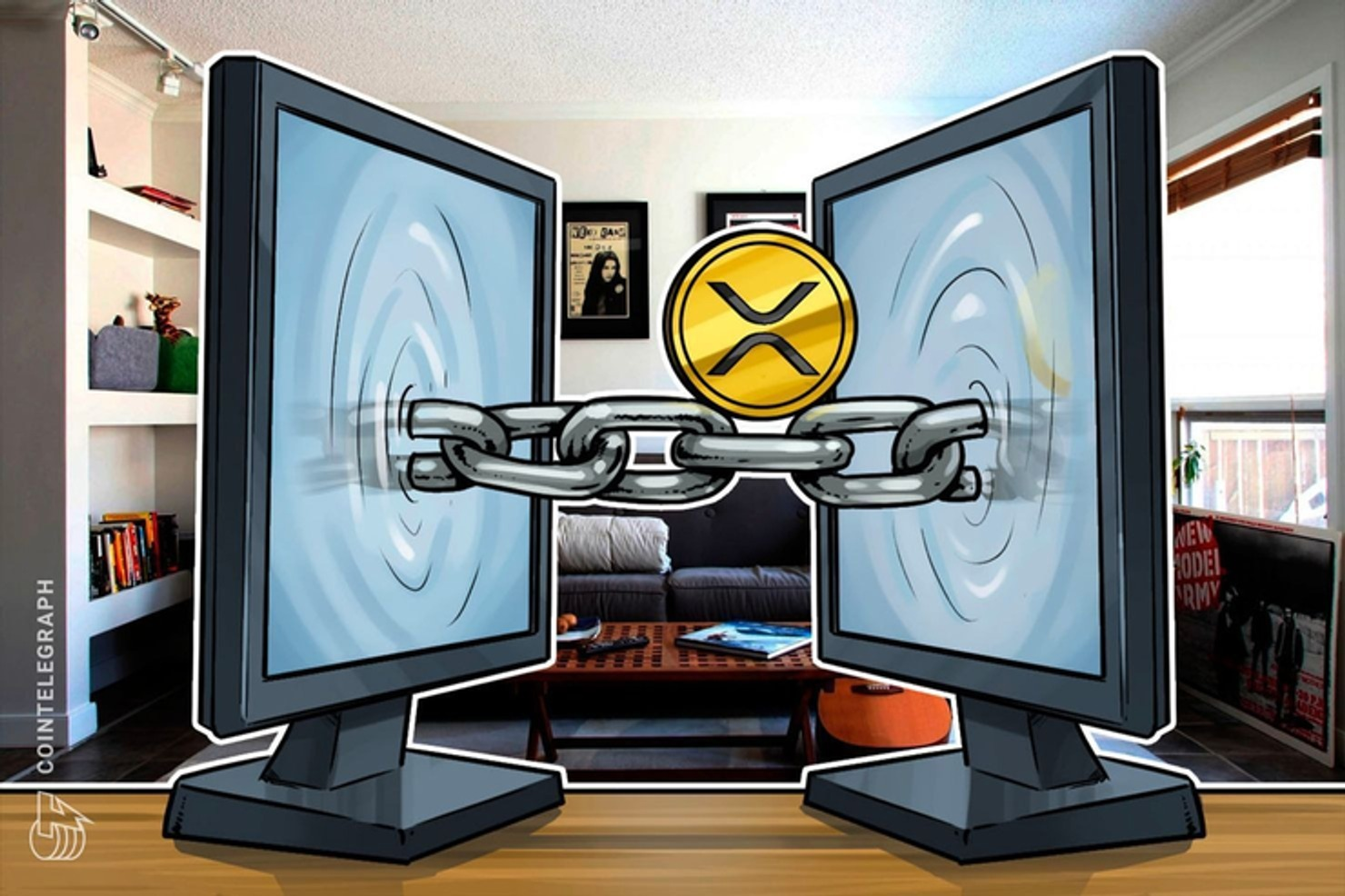『アフタービットコイン』の著者であり、決済・送金分野の専門家である中島真志教授は、仮想通貨XRPのクロスボーダー決済での利用拡大に向け、銀行が共同でインターバンク取引専門の仮想通貨取引所設立を提唱した。
中島氏は、10日に東京で開催された「XRP Meetup Japan」に登壇。国際送金システム「SWIFT」とリップル、デジタル通貨の未来について語った。
ライバルSWIFTの攻勢
中島氏は、リップルの登場によって、伝統的なクロスボーダー送金のインフラだったSWIFTにも変革が起こっていると語った。
SWIFTが開発した「グローバル・ペイメント・イノベーション(GPI)」の登場だ。中島氏によれば、9月時点で660行がGPIに参加し、クロスボーダー送金の60%がGPIを利用している。36%が「5分以内」、「1時間以内」が18%となっており、送金スピードがGPIで上がっている点を中島氏は指摘する。
「わざわざ新しいシステムを入れて、リップルを使わなくてもいいじゃないかという考えも出てくるだろう。ただSWIFTもリップルという競争相手が出たからこそ、改善に本腰を入れたのではないかと思う」
「スピードよりも流動性の節約」
そのためリップルの方では、スピードではなく、流動性ということを訴えるようになっている。
リップルはXRPをブリッジ通貨として、各法定通貨とをつなぐ送金手段としている。従来のクロスボーダー送金で、米ドルが担っていた役割を代替するものだ。
現在は各銀行は米ドルの流動性を持つため、ドルを準備している。リップルのガーリングハウスCEOは今年1月、こういった準備金が10兆ドルにものぼると指摘し、XRPによる効率化でこういった資金をほかの目的で使うことができると訴えた。
銀行がODLを使わない理由
ただXRPを使った技術「ODL」を導入している銀行はまだ少ない。
中島氏は9月に英ロンドンで開催されたSWIFTのイベント「Sibos」で、金融機関にXRPを使わない理由を調査した。
1つは「銀行間のインターバンク取引をいったん外に出すことに抵抗がある」(中島氏)ことだ。XRPを使う場合には、法定通貨とXRPを交換する過程で、仮想通貨取引所が関与することになる。
またマネーロンダリングの懸念も大きいという。
銀行と取引をした仮想通貨取引所がマネーロンダリングに関与していた場合、銀行側にも飛び火する懸念があるためだ。マネーロンダリグに銀行が関係していたと判断されれば、銀行にも高額の罰金を科される可能性がある。
「銀行による仮想通貨取引所」を提唱
「私が提案したいのは、リップルネットに参加する銀行が共同で設立する仮想通貨取引所だ」。
中島氏は、外部の取引所の関与がボトルネックとなってるのであれば、銀行自身がXRPと法定通貨を交換する取引所を運営することだ。
中島氏が提唱する取引所は、個人向けのリテール取引は行わず、インターバンク取引に特化する。
採算面についても「銀行側で送金のためのドル預金が必要なくなる。そういうコスト削減が期待できる」と指摘。また今後リップルのネットワークに参加する銀行が拡大すれば、ペイするものになっていくとみる。