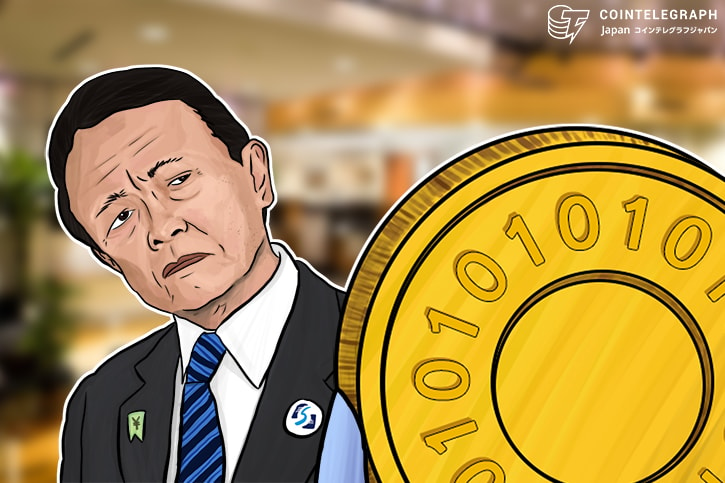金融庁は4月3日、1月14日から2月13日かけて行っていた新しい仮想通貨規制に関するパブリックコメントの結果を公表した。172の個人・団体から398件のコメントが寄せられた。
既報の通り、4月3日の官報で仮想通貨交換業に関する内閣府令が発表されており、新しい仮想通貨規制は5月1日から施行されることになっている。
今回の新しい仮想通貨規制は、セキュリティトークンオファリング(STO)、仮想通貨ウォレット・カストディ、仮想通貨デリバティブ取引など多岐にわたる。その中から、特にユーザーからの注目度が高かった、仮想通貨の証拠金取引などの規制について、金融庁の見解をみてみたい。
仮想通貨デリバティブ取引について
まず、金融庁は仮想通貨デリバティブ取引について、「社会的意義が見出し難い」とコメント。仮想通貨デリバティブについて厳しい視線を向けていることが伺われる。
「暗号資産を用いたデリバティブ取引については、原資産である暗号資産の有用性についての評価が定まっておらず、また、専ら投機を助長しているとの指摘もある中で、その積極的な社会的意義を見出し難いものと考えられます」
証拠金取引の上限2倍規制の理由
証拠金取引の規制については、政令案が出た時点から、証拠金倍率の上限が現状の4倍から2倍に変更される点が大きな注目を浴びた。
金融庁は、高レバレッジの仮想通貨の証拠金取引は顧客保護などの観点から問題があると指摘している。
「個人顧客を相手方とする高レバレッジの暗号資産を用いた証拠金取引については、①顧客保護(ロスカット・ルールが十分に機能せず、顧客が不測の損害を被るおそれ)、②業者のリスク管理(顧客の損失が証拠金を上回ることにより、業者の財務の健全性に影響が出るおそれ)、③過当投機の観点から問題があると考えています」
さらに、金融庁で設置された研究会内の議論で、「証拠金倍率については、(中略)仮想通貨の価格変動は法定通貨よりも大きいことを踏まえ、実態を踏まえた適切な上限を設定することが適当と考えられる」「証拠金倍率の上限については、(中略)2倍とすることを基本に検討すべきとの意見があった」といって点を踏まえ、今回の規制を整備したと説明している。
海外業者へのユーザー流出への懸念について
また証拠金取引の規制強化で、国内の業者から海外業者にユーザーが流出するのではと懸念に対しては、日本での無登録業者に対しては警告などの対応するとともに、利用者にも注意喚起をすると回答。国内で登録しない海外業者に対しては、海外の関係当局とも連携して、対応するとしている。
ゼロカット方式導入について
追証が発生しない「ゼロカット方式」の導入については、「顧客が損失の可能性を顧みずにリスクの高い取引を行うことを誘引するおそれがあることや、業者のリスク管理等の観点を踏まえ、慎重に考えるべきもの」との姿勢だ。
2倍規制の見直しはあり得るのか?
2倍の上限規制の見直しの可能性については、必要な場合には規制の見直しもあり得るとしている。
「一般論として、暗号資産を用いた証拠金取引を取り巻く状況の変化等に応じ、必要な場合には、規制の見直しを検討していくものと考えられます」
また板取引については「今般の改正は、暗号資産関連デリバティブ取引についていわゆる板取引を禁止するものではありません」と回答している。