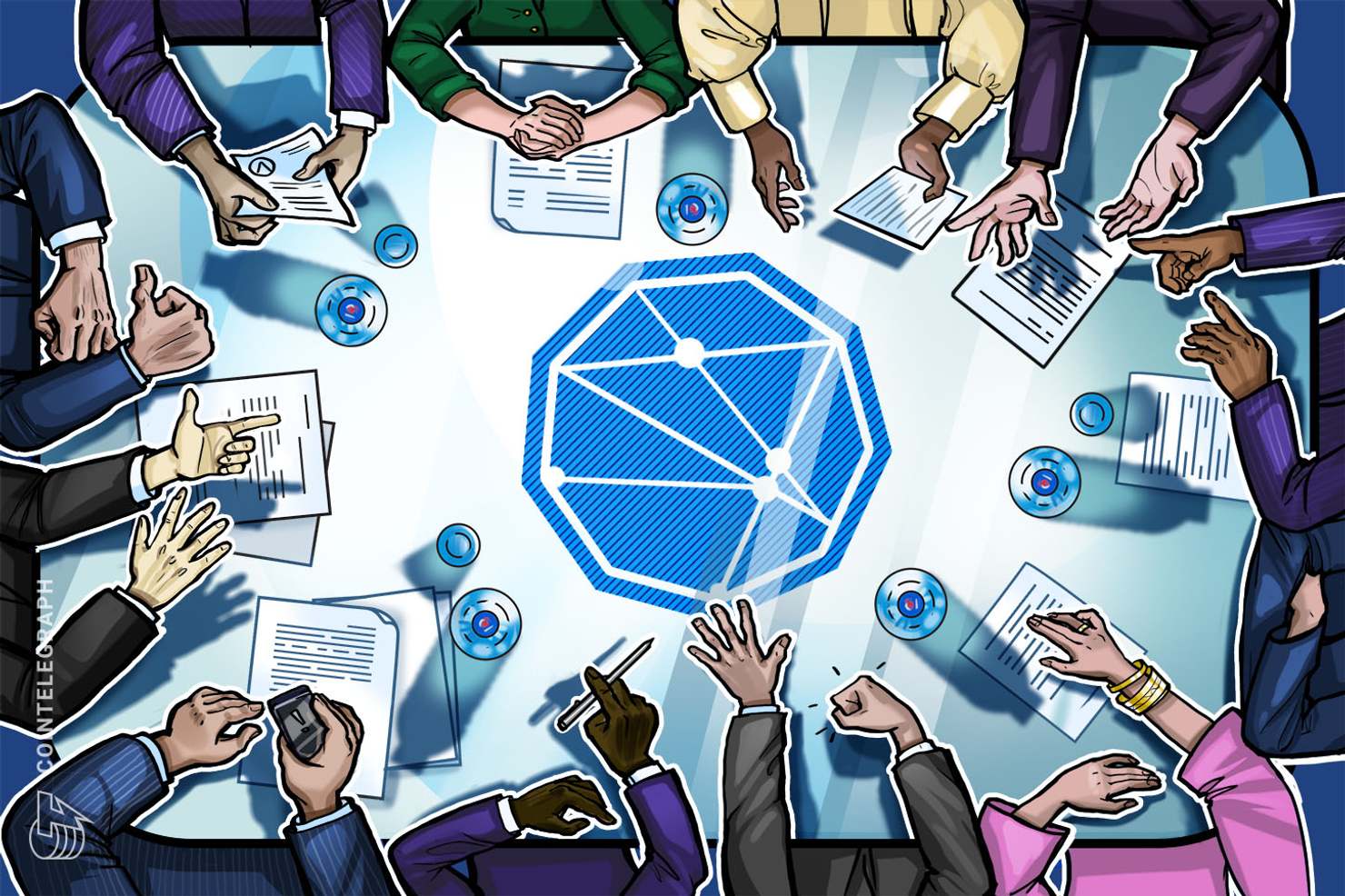金融庁は8月31日、令和2年度の新たな金融行政方針「コロナと戦い、コロナ後の新しい社会を築く」を発表した。この中で仮想通貨(暗号資産)やブロックチェーン、中央銀行デジタル通貨(CBDC)について言及した。
金融庁は以下の3点を重点課題とすることを公表した。
1.「コロナと戦い、コロナ後の新しい社会を築く」
2.「高い機能を有し魅力のある金融資本市場を築く」
3.「金融庁の改革を進める 」
マネロン対策
仮想通貨については2の中の項目にある「市場監視」の中で、アンチマネーロンダリングやテロ資金供与対策の中で言及。マネロンやテロ資金供与については、「預金取扱金融機関へのモニタリングを強化するとともに、資金移動業者や新しい業態についてもオンサイトも含めモニタリングを実施する。」と表明。
これまでのモニタリングの実施結果を踏まえて、今後、新たに論点の整理を行うとしたうえで、仮想通貨については国際的な文脈の中で以下のように指摘した。
「マネロン・テロ資金供与対策に関する国際的な議論の中では、暗号資産やステーブルコインが論点となっている。金融庁が共同議長を務めるFATFコンタクト・グループにおける、暗号資産に係る新たな基準の実施、暗号資産・ステーブルコインについてのルールの追加等において主導的な役割を果たす。」
ブロックチェーンでは国内外の議論主導
ブロックチェーンに関しては1の「コロナ後の新しい社会を築く」の中で言及。コロナ後に「コロナ後の顧客ニーズに応える金融サービスづくり」が重要と強調した。
この中の項目の一つに「金融デジタライゼーション」があり、ブロックチェーンは今年3月に始まったブロックチェーンのガバナンスを議論するイニシアティブ「ブロックチェーン・ガバナンス・イニシアティブ・ネットワーク(BGIN)」でデジタル・イノベーションを支援するものとして言及された。
「ブロックチェーン等の分散型技術の金融システムへの応用についても、Blockchain Governance InitiativeNetwork(BGIN)の活動やブロックチェーン「国際共同研究」プロジェクトを通じて国内外の議論を主導していく。」
BGINは金融庁やアイルランド財務省といった規制当局のほか、コインベースやクラーケンといった仮想通貨取引所、イーサリアム財団、ジョージタウン大学の松尾真一郎教授などの研究者らが約20人が参加している。
また、ブロックチェーンの採用には直接言及はしていないものの、「ハンコ問題」については「、デジタル化への障壁となっている従来の書面・押印・対面を前提とした慣行の見直し」が必要としており、オンラインで完結する非対面サービスの普及に向けた取り組みを進めるという。
中央銀行デジタル通貨に関しても「金融デジタライゼーション」の中でクロスボーダー決済の環境整備のために「財務省とも連携しつつ、日本銀行の検討に貢献する」とした。
金融庁長官のサトシ賞賛
金融庁は先日、ブロックチェーンカンファレンスの「FINSUM」を開始し、BGINについての議論を開催している。この中では、暗号資産やブロックチェーンの規制をインターネットにおける規制をモデルにして構築していこうという議論が交わされた。
ブロックチェーンや、最近勃興著しい分散型金融(DeFi)といった分野は、グローバルなネットワークの中で開発や利用が進んでいる分野だ。そこをいかに管理していくかというのが、どのような設計をグローバルに設けるのかが今後の課題になっていく。そこで開発者や規制当局、事業者が同じテーブルで議論を進めていくマルチステークガバナンスの形をそこに導入しようとしている。
またFINSUMで大きな注目を集めたのが金融庁長官に就任したばかりの氷見野良三氏のスピーチだ。氷見野長官はスピーチの中で、「サトシの夢はより今日的意義があるものだと思う」と語り、ビットコインとブロックチェーンのシステムが持つ意義は社会にとって非常に大きいものだと主張した。規制当局のトップである氷見野長官のビットコインに対する注目度の高さは、今後の規制における柔軟性を期待させるものだといえるだろう。