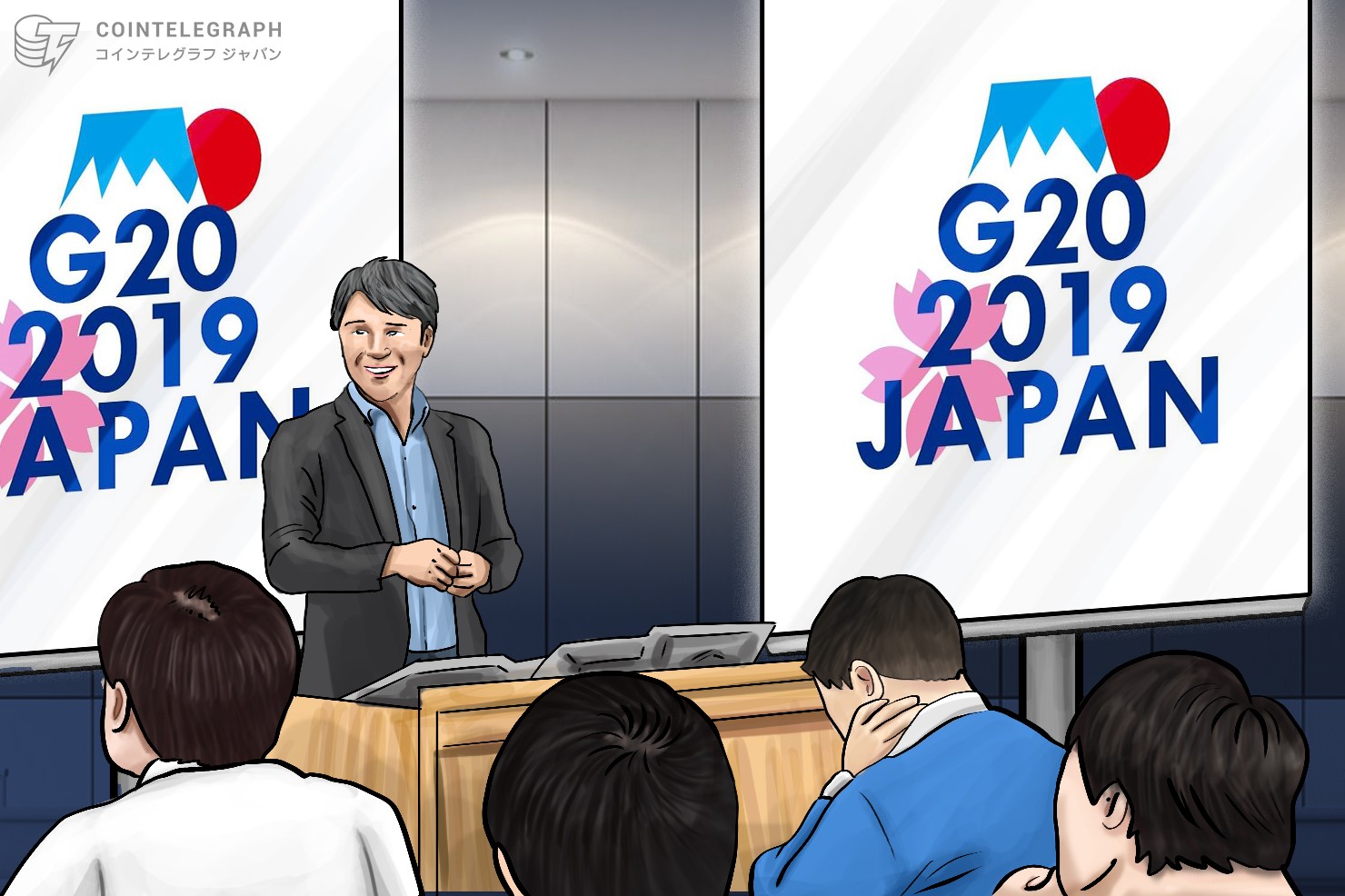6月8、9日に開催されるG20福岡財務大臣・中央銀行総裁会議で最も重要な論点の一つが「仮想通貨のマネーロンダリング規制」だ。テロやイスラム過激派の資金の供給源である「黒いお金」になっているとの指摘から、世界が足並みをそろえて対策をする必要がある。
ただ、そもそも仮想通貨でマネーロンダリングが注目されているのはどのような仕組みからなのだろうか。本連載ではG20に向けて、仮想通貨とマネーロンダリングというテーマの注目点を、仮想通貨の法務相談の専門家である法律事務所ZeLoの高井雄紀弁護士に予想してもらった。
テロ資金への流入防ぐためのガイドライン策定へ
マネーロンダリングは、犯罪などに関わり、表には出せない「黒いお金」を何らかの手段によって、「きれいなお金」にすることで世の中で堂々と使えるようにする手法のことだ。
このマネーロンダリングを防ぐために、本人確認の厳格化などを通して資金が回りにくくするといった「流動性」を低くする手法が取られる。また、銀行送金となると、犯罪収益移転防止法(犯収法)などによって送金元、送金先のお金の流れを後から補足することでマネーロンダリングを防ぐ方法をとっている。
仮想通貨では資金の流動性が高く、マネーロンダリングがしやすいという点があるのだ。高井弁護士は、
仮想通貨ではまとめて海外への送金も簡単である上、秘密鍵などの特性上、送金したお金の証明番号と送金者が紐づいていません。トランザクション(取引)の形跡は残るものの、送金者を補足することができない。これが問題なのです。
と指摘する。

国際的な問題に発展しやすいことから、高井弁護士はG20では仮想通貨のマネーロンダリング規制について各国の体制について定める「ガイドライン」について合意されるのではないかと予測する。
日本はなぜ躍起?
G20が日本で開催されることは、日本政府にとって好機となる。盤石のマネーロンダリング対策を金融活動作業部会(FATF)に示したい思惑があるからだ。それは今から10年前に実施された「第三次FATF対日相互審査」厳しい結果になったことが背景にある。
 (出典:警察庁刑事局組織犯罪対策部)
(出典:警察庁刑事局組織犯罪対策部)
2009年にマネーロンダリングの審査で行われた「40の勧告」の中で日本は重要勧告である「顧客管理」などに「×」がつく悪い結果になったために、今回は汚名を返上したいと考えている。
高井弁護士も日本の規制について「特に罰則が他国に比べて非常に緩かった」と指摘する。
G20の注目は「ガイドライン」の策定のレベル感
「ガイドライン」とは日本を含め、世界各国がマネーロンダリング対策(AML)を実施する際の基準となるもので、FATFもこの基準の早期策定を目指している。
高井弁護士は「『ガイドライン』の規定がどのレベルで決定されるか」が注目点だと指摘する。今回の合意でガイドラインが前回のFATF調査で優秀だった国ベースの厳しい基準で策定されるのか、多くの国が規制しやすい緩い最大公約数的な基準をとるかが注目点としてあげられる。
マネーロンダリングの規制方法は世界でバラバラです。仮想通貨では世界で統一した取り組みでないと意味がありません。1カ国でも足並みが揃わないと、規制の抜け穴になってしまいます。そのための取り決めがガイドラインです。
ガイドラインの違反による罰則は?
こうしたガイドラインに違反した場合には何か罰則の適用も想定されるのだろうか。高井弁護士は「罰則までいくかはわからない。ガイドラインに法的な拘束力を持たせることはないだろうが、守らない場合に『世界の金融の動きから取り残される』という危機感から各国も守らざるを得なくなる」と話す。
守られなければ「あなたの国は危険だから」銀行送金を認めない、という措置が取られることも考えられます。これは十分な「経済制裁」です。
こうしたガイドラインの規制に影響を大きく受けると予想されるのがウォレットのサービス提供者である仮想通貨カストディ業者だ。つい先日5月31日に成立し、2020年上旬までに施行される見通しとなった改正法では、仮想通貨交換業規制のうち仮想通貨の管理に関する規制が適用されることになった。マネロンなどを意識してカストディ業者も本人確認を徹底する必要性が出てきた。
しかし、こういった本人確認やスリーラインディフェンスを構築するのは非常に大変で、事業のハードルになり、中小・零細ウォレット業者の売り上げにも影響してくる。高井弁護士も「かなり大変だが、しっかり規制しなければ抜け道になる」という。

ただ、いきなりカストディ業者を仮想通貨業者と同等に扱うような厳しい規制は考えにくく、改正法施行後一定期間は、
カストディ業者に対する規制運用方針を緩やかにするなどの動きが 予想されます。その間に各社はアンチマネーロンダリングのための部署の設置を進めなければいけません。
と話す。
一方で高井弁護士は「こうした規制による業務整備の課題を緩和させるような動きも出てくる」と予測する。
その一つの例がオンライン上で本人確認ができるe-KYCだ。従来は書類の郵送などによってしか本人確認ができなかったがそれがオンラインで済ませられることによって事業者側の負担が軽くなった。こうした手続きの簡素化を進めることで仮想通貨業界の円滑化を図るための取り組みにも期待したいという。
しかし、次から次に生まれるウォレット業者を規制するには秘密鍵やマルチシグなどまだまだ課題は多い。さらにガイドラインを各国がどのレベルまで遵守するのかといった課題もある。
各国の合意がどのレベルで行われるのか。ガイドラインを策定したあとの行動規範なども課題になってくるだろう。G20の議論に注目したい。