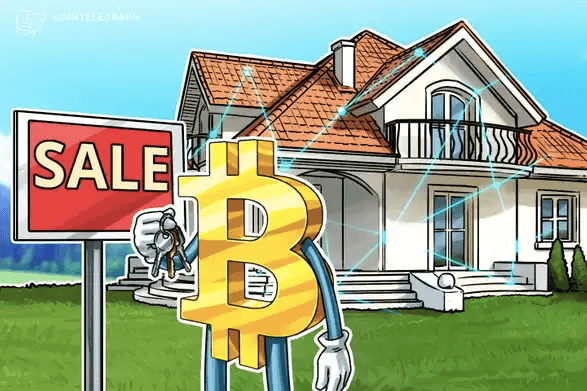不動産投資とは、マンションやアパートなどの物件に投資をして家賃収入や売却益を狙う投資だ。「収入源を増やせる」「生命保険代わりになる」など、不動産投資には多くのメリットがある。
本記事では、不動産投資で得られる利益の種類やメリット、デメリットについてわかりやすく解説する。
不動産投資の利益の種類
不動産投資で得られる利益には「インカムゲイン」と「キャピタルゲイン」がある。インカムゲインとは、資産を保有中に得られる収益のことだ。株式であれば配当金、債券であれば利子がインカムゲインにあたる。不動産投資におけるインカムゲインは、家賃収入となる。
対してキャピタルゲインは、不動産を購入したときよりも高い価格で売却したときに発生する利益のことである。たとえば3000万円で購入した物件を3500万円で売却できたら、500万円のキャピタルゲインを得られる。将来的に価値の上昇が見込める不動産に投資をすると、大きなキャピタルゲインを得られる可能性がある。
2021年12月現在の日本では、バブルの頃のように不動産価格が大きく上昇する可能性は低いといわれている。そのため不動産投資は、安定した家賃収入が得られる物件に投資をするのが基本である。
収益性のリスクのバランスから考えると、預貯金や債券はローリスク・ローリターン、仮想通貨やFXはハイリスク・ハイリターンといわれているのに対し、不動産投資はミドルリスク・ミドルリターンといわれている。これは、きちんとリスク対策をしていれば安定した家賃収入が得られるためだ。

不動産投資の利回り
投資をする際は、利回りの計算が欠かせない。不動産投資における利回りには「表面利回り」と「実質利回り」の2種類がある。それぞれの計算方法は、以下のとおりだ
- 表面利回り:年間の家賃収入 ÷ 物件価格
- 実質利回り:(年間の家賃収入-諸経費) ÷ (物件価格+購入時の諸経費)
表面利回りは、年間の家賃収入を物件価格で割って算出するのに対し、実質利回りは、購入時や賃貸経営時の諸経費も含めて利回りを計算する。
たとえば年間の家賃収入が300万円、諸経費が50万円、物件の購入価格が3000万円、購入時の諸経費が250万円であるとしよう。
この物件に投資をした場合、表面利回りは「300万円÷3000万円=10%となる。一方で実質利回りは「(300万円-50万円) ÷ (3000万円+250万円)≒7.7%だ。
表面利回りは諸経費が計算に含まれていないため、建物の価値を大まかに把握する際にしか利用できない。不動産投資において経費の発生は避けられないため、投資判断をするときは実質利回りを計算することが大切だ。
不動産投資の投資先
不動産投資における主な投資先は、以下のとおりだ。
- マンション(区分所有、一棟所有)
- アパート
- 戸建て住宅
- 駐車場 など
区分所有とは、マンションの中にある1戸(1部屋)に投資をすることだ。不動産投資をはじめる場合、ワンルームマンションの区分所有またはアパートから始めるケースが少なくない。
なおREIT(不動産投資信託)という金融商品を購入することで、間接的に不動産投資ができる。REITは、複数の投資家から集めた資金でオフィスビルや商業誌施設などに投資をし、得られた家賃収入や売却益を出資額に応じて投資家に還元する金融商品だ。
不動産投資をはじめる際は、数百万〜数千万円ほどの資金が必要となるのが一般的である。一方でREITは、現物不動産投資よりも少ない資金で始められる。

不動産投資のメリット
不動産投資には、数多くのメリットがある。代表的なメリットは、以下のとおりだ。
- 収入源を増やせる
- 団体信用生命保険に加入できる
- 所得税や住民税を節税できる場合がある
- ローンを活用することで手持ち資金以上の物件に投資できる
- 相続対策になる
- インフレリスク対策になる
収入源を増やせる
不動産投資をすることで、家賃収入という給与収入とは別の収入源を確保できる。終身雇用が崩壊し、勤続年数を重ねるだけでは給与が増えていかない現代において、収入源を増やせることは大きなメリットといえるだろう。
また老後生活においては、投資物件から得られる家賃収入が年金代わりになるため、老後の資金不足を心配することなく豊かな生活を送れる可能性がある。
団体信用生命保険に加入できる
団体信用生命保険(以下、団信)とは、不動産投資ローンを借り入れた人が亡くなったときに保険金でローンが完済される保険だ。がんや三大疾病(がん・心筋梗塞・脳卒中)と診断されて、所定の状態になった場合も残債が0円となる団信もある。
団信に加入すると、万一のことがあった場合、ローンの返済義務がない物件を残された家族に引き継げる。残された家族は、物件から得られる家賃収入によって生活費や教育費などを賄えるだけでなく、物件を売却してまとまった現金に手にすることも可能だ。
所得税や住民税を節税できる場合がある
賃貸経営において赤字が発生した場合、給与所得をはじめとした他の所得と相殺(損益通算)することで、所得税や住民税の負担を軽減できる。
不動産投資の経費の1種に「減価償却費」がある。減価償却費とは、建物や設備などの取得金額を、買ったときにまとめて経費に計上するのではなく、毎年少しずつ経費とする会計処理だ。減価償却費を経費に計上することで、本来の収支が黒字であっても帳簿上は赤字になることがあり、損益通算をして所得税や住民税の負担を軽減できる場合がある。

ローンを活用することで手持ち資金以上の物件に投資できる
アパートやマンションなどの投資をする際は、金融機関から不動産投資ローンを借り入れるのが一般的だ。不動産投資ローンを借り入れることで、自己資金以上の物件を購入できる。他人の資本を利用して投資効果を高めることを「レバレッジ効果」という。
投資は、いくら利回りが高くても投資元本が少ないと、高い収益は期待できない。不動産投資であれば、ローンを借り入れて投資元本を増やし高額の不動産に投資をすることで、高い収益が期待できる。

相続対策になる
亡くなった人が残した財産を引きついだ人には、相続税が課せられることがある。相続税を計算する際は、引き継ぎの財産の価値が評価される。
相続した財産が現金だった場合、口座の残高で価値が評価されるため、相続税を計算するときの価値は時価と同じになる。一方で不動産の場合、価値が時価よりも低く見積もられるため、現金を引き継ぐよりも相続税を軽減できる可能性がある。
インフレリスク対策になる
インフレリスクとは、将来的に物価の価値が上がることで、相対的に貨幣の価値が下がってしまうリスクのことだ。たとえば1本100円のジュースが、20年後には1本200円に値上がりしていたとしよう。ジュース1本の価値は、100円から200円へと2倍に増えている反面、現金100円の価値はジュース1本ぶんからジュース0.5本分に減っている。
アパートやマンションなどの不動産はモノであるため、インフレが起こると不動産の価値は基本的に上昇する。資産を、現金から不動産にシフトすることでインフレリスク対策になる。
不動産投資のデメリット
一方で不動産投資には、以下のデメリットがある。
- 初期費用やランニングコストがかかる
- 空室の発生や家賃滞納などのリスクがある
- 換金性が低い
初期費用やランニングコストがかかる
不動産投資を始める際は、頭金や購入時の諸費用などを支払う資金を準備しなければならない。2021年10月現在、フルローンで投資物件を購入するのは困難だ。本人の年収や勤続年数などにもよるが、物件価格の1〜3割程度の頭金を準備しなければ、金融機関は融資してくれないといわれている。
また不動産投資では、以下のような初期費用がかかる。
- 印紙税
- 登記費用(登録免許税・司法書士に対する報酬)
- 不動産会社に支払う仲介手数料
- 火災保険や地震保険の保険料
- 不動産投資ローンの借入費用(事務手数料・保証料) など
初期費用の目安は、物件価格の8〜10%程度だ。たとえば物件価格が4000万円であった場合
初期費用は、320万〜400万円が目安である。
また物件を購入したあとも、固定資産税や都市計画税、管理費、修繕費などの維持費用がかかる。
空室や家賃滞納などのリスクがある
不動産投資をする際は、以下のようなリスクに対処する必要がある。
- 空室が発生するリスク
- 入居者に家賃を滞納されるリスク
- 建物を修繕するリスク
- 建物が災害の被害に遭うリスク
- ローンの金利が上昇するリスク など
たとえば空室が発生した場合、速やかに次の入居者を見つけなければ、長期間にわたって家賃収入が減ってしまいかねない。経年劣化や自然災害などが原因で建物に損害が生じ、多額の修繕費用が発生する恐れもある。
不動産投資のリスクは「信頼できる管理会社に管理を委託する」「保険に加入する」などの方法で対処が可能だ。不動産投資で安定した利益を得るためには、リスクに適切に対処する必要がある。
換金性が低い
不動産を売却して換金するは、不動産会社を通じて売りに出し、買い手を探す必要がある。買い手が見つかるまで時間がかかる場合もあるため、株式や投資信託のようにすぐに売却して現金に換金できるわけではない。
そのためまとまった金銭が必要になっても、不動産を現金化して支払いに充てるのは困難である点に注意が必要だ。