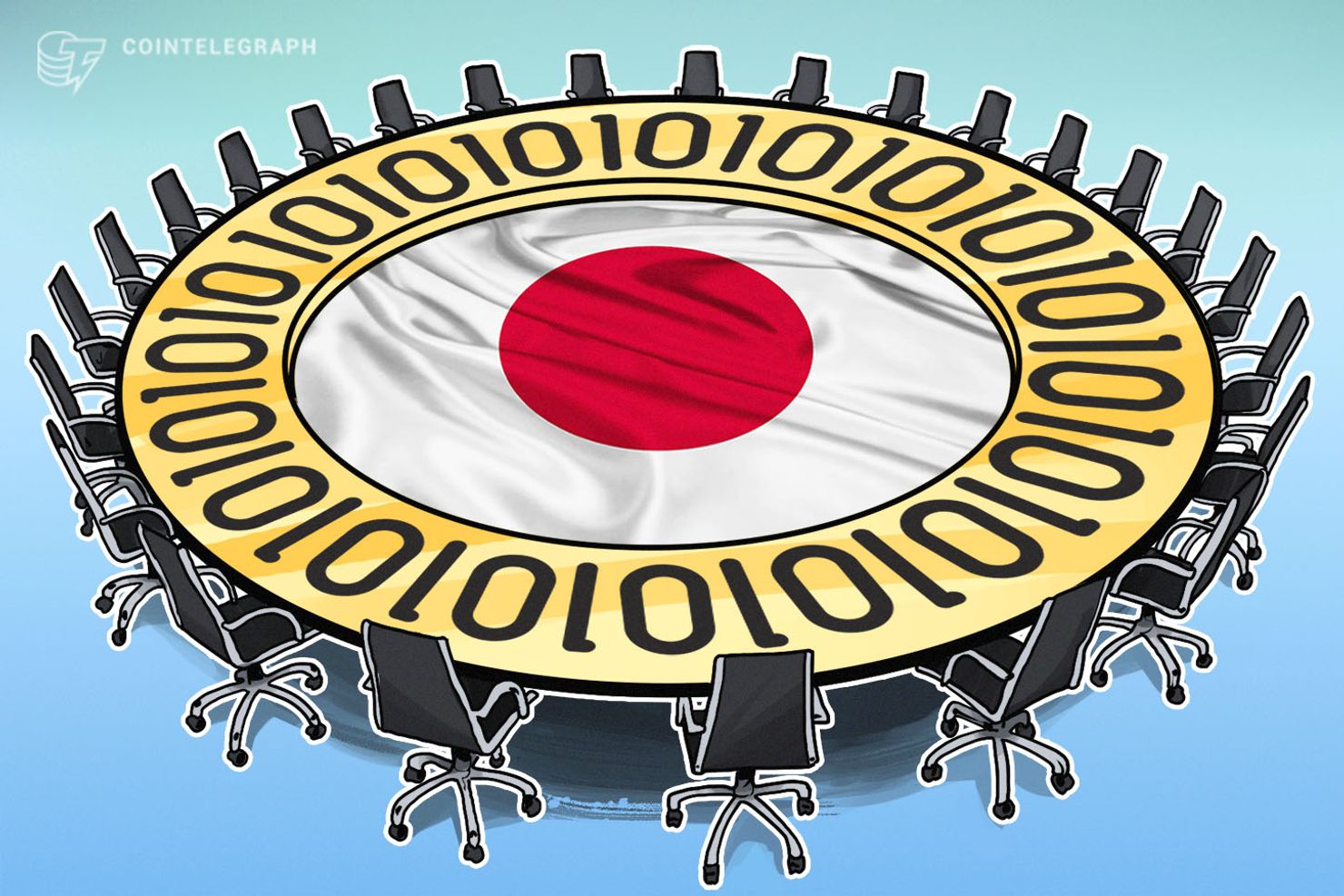金融庁の「仮想通貨交換業等に関する研究会」の第6回の会合が10月3日に開催された。仮想通貨交換業者で作る業界団体、日本仮想通貨交換業協会の奥山泰全会長は、テックビューロでのハッキングによる仮想通貨流出事件を受け、仮想通貨を管理するネットワークとをほかのネットワークと分離するといった自主規制を検討する考えを示した。
奥山会長は、今回の流出事件を受け、3つの自主規制を検討する考えを明らかにした。
1)ブラウザやメールなどの社内利用についての制限や社内の仮想通貨を管理するネットワークを分離することを自主規制として設ける。2)またホットウォレット、コールドウォレットの定義を協会として行い、その上でホットウォレットに必要以上に仮想通貨を保持しないようにする。3)外部の有識者を招いたセキュリティ面の技術委員会を早急に立ち上げ、業者側の知見を補う形にする。
交換業協会は前回の金融庁の研究会で自主規制案の概要について公表しているが、こういった対策を協会の内部で検討して追加する考えだ。
またテックビューロの不正流出事件では、不正アクセスが9月14日に発生し、当局への報告は9月18日まで遅れた。委員からは「交換業者側では日時で残高確認をしていたはず、またエラーの報告もあったはずだ。残念ながら事業者側がインシデントに気づいても即座に報告しない状況も想定される」と指摘し、当局側が交換業者の異常な残高の変化を検知して対応する選択肢もあり得るとの声も出た。
仮想通貨交換業の規制について議論
第6回の会合では、金融庁の事務局側から具体的に議論していく対象として3つの分野を挙げている。
ア)仮想通貨交換業に係る規制
イ)仮想通貨を原資産・参照指標とするデリバティブ取引に係る規制
ウ)ICOに係る規制
3日の会合では、仮想通貨交換業に係る規制について議論が行われ、「問題のある仮想通貨の取り扱い」や「顧客財産の管理・保全の強化」などについて意見が交わされた。
匿名性の高い仮想通貨については、マネーロンダリングに悪用される懸念があることから、取り扱いを禁止するべきとの指摘が出た。その一方で、匿名性を求める利用者のニーズや研究開発用途でのニーズがあるとし、一定の本人確認をした上で取り扱う道を残す方法も検討するべきとの意見も出された。
顧客資産の保全・管理については、顧客から預かった仮想通貨を信託で管理し、倒産リスクに対応するアイデアなどが議論された。ただ実際に仮想通貨を信託会社が受け付けてくれるのか、また受け付けるとしても仮想通貨の種類が限られるのではないかとの声も出た。破綻時に顧客資産が保護されるために、一定の優先的な弁済の権利を付与するといった考えも示された。
仮想通貨の流出事案での顧客資産の保護については、サイバー保険の活用や、一定の純資産額の保持を求める考えについて議論が行われた。
また交換業者について最低資本金1000万円以上という現行ルールについて「預かり資産で地銀の下位行並みの業者もあり、低すぎるのではないか」との意見もあった。一方で、イノベーションのタネを絶やさないためには、消費者のリスクがないところでは規制を柔軟にするなど、リスクに応じた規制を検討するべきとの意見も出た。