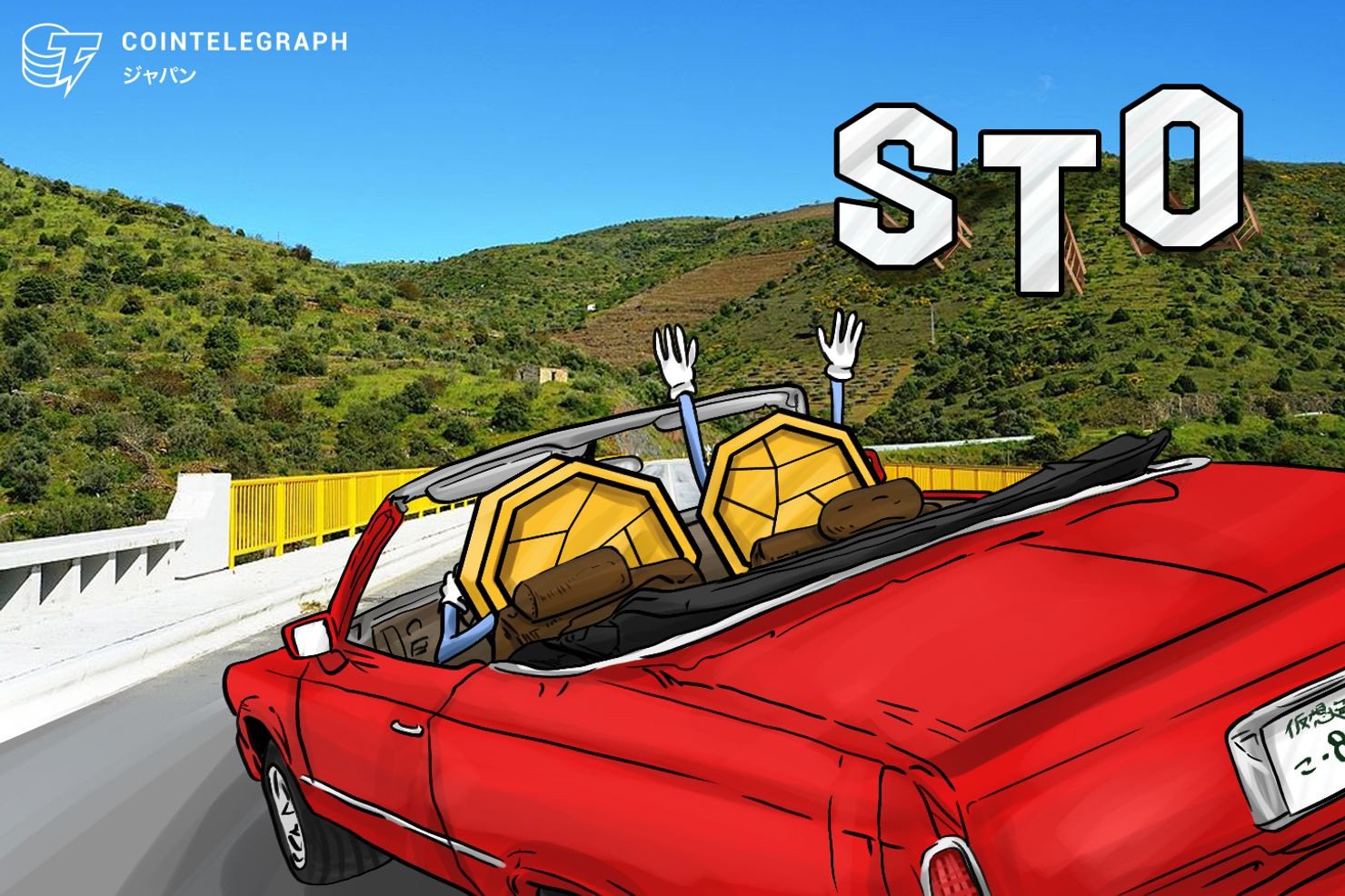日本におけるセキュリティトークン・オファリング(STO)はどのように活用されていくのか。日本におけるプレイヤーたちが、ブロックチェーンイベント「FINSUM」で、その展望を語った。
25日に開催されたセッション「STOが拓く不動産市場の未来」の中で、不動産分野におけるセキュリティトークンの可能性が議論された。
三井不動産ソリューション企画室長の湯川俊一氏は、STOに期待する点として、より多様な不動産投資につながる点を挙げる。
「多様な不動産の存在が多様な人を集め、街が活性化していく」と指摘し、最先端のオフィスビルからベンチャー企業向けのオフィス、一流ホテルからバックパッカー向けのもの、高級なレストランから個性のある個人店まで、街づくりの中では様々な不動産が存在すると語る。しかしこれまで投資対象となるのは大規模な開発案件だけだったが、それがSTOで変わる可能性があるという。
「これまで大型のオフィスビルやホテル、ショッピングセンターしか投資対象にならなかった。魅力のある応援したい小規模な店舗や歴史のある建造物といったものは、投資対象ではなかった。STOして注目しているのは、こういった不動産が投資対象となることだ」
不動産証券化がより小口化できることで、今まで気づかない投資の可能性が出てくることが期待できるとみる。
ただ、従来の不動産証券化が対象とするようなオフィスビルやショッピングセンターの大規模開発案件へのSTO適用については、慎重な見方だ。「現状のREITも優れた仕組みであり、マーケットでも機能している。STOに置き換えるほどの優位性があるかは、検証がまだ済んでいないところだ」と話す。
もちろん、将来的にデジタル化の流れが加速すれば、STOという手段もあり得るが、現状では中立的な立場だと話す。
ブロックチェーンによる直接金融市場の拡大
野村ホールディングス執行役員でイノベーション推進担当の八木忠三郎氏は、STOによって直接金融市場がますます拡張されたものになると指摘している。
これまでの直接金融市場は、上場企業や富裕層の投資家、優良物件の不動産というものに限定されていた。これにブロックチェーン技術を適用することで、「直接金融市場のヒト・モノ・カネの滞留を解消する動きが出ている」と強調した。

出典:FINSUM
これまで上場企業に限られたプレイヤーが非上場企業にも拡大し、モノとして投資先も優良不動産だけでなくはアートといった分野にも拡大するというものだ。投資先が多様化することで、リターンも多様化していき、ブロックチェーンが多様な価値の交換を可能にする可能性があるという。
「買う」「借りる」以外の選択肢も
TMI総合法律事務所の成本治男弁護士は、ファンマーケティングや不動産利用権ちった3つの分野で不動産STOが期待できるのではないかと展望を語った。
1つは証券化商品としてのセキュリティトークンの可能性だ。REITではできなかった、より小口でローリスク・ローリターンの商品を提供することができれば、個人の預貯金の受け皿となる長期投資向け商品になるだろうと語った。現在のREITは適格投資家や機関投資家が中心だが、個人を取り込めるような商品展開ができれば、「REITを超えるマーケットになる可能性もある」と強調した。

出典:FINSUM
またファンマーケティングの文脈で「よりハイブリッドな投資の仕方」もあり得ると、成本氏は語る。文化施設やスポーツ団体の施設、観光施設といった物件と、非経済的なリターンを組み合わせたものだ。
もう1つの可能性は、新型コロナウィルス禍のワーケ―ションなどの文脈で、不動産の利用権をSTOで提供することだ。
「不動産ではこれまで『買う』か『借りる』かしなかったが、一定の投資をすれば、何日か泊まれるというような形も考えられる。買うか借りるか以外の住み方に対応した契約形態や投資がトークンという形で提供できるのではないか」
規制面での対応の課題
様々な可能性が議論されたが、それでもまだ実際に実現するとなれば、解決しなければならない課題はまだ多いと、参加者らは議論する。
野村ホールディングスの八木氏は、これまで構築してきたシステムにおいて、新しい権利の移転や違う流れを作ることは、最初のハードルはかなり高いものになるだろうと話す。
また成本氏は、改正金融商品取引法のもとで、セキュリティトークンが1項有価証券という取扱になったことは、参加者が限定されることで「しっかりしたプレイヤーが入ってくる」メリットがある一方で、小規模な商品の設計は難しいとも指摘する。
「一定の限度を決めて、スタートアップを含めてトライできる環境なども検討して欲しい」と語り、マーケットのニーズや成長と対話しながら、バランスの良い規制を構築する必要性を語った。
三井不動産の湯川氏は、過去のREIT市場形成の事例をもとに、「STOを使うことが信用に値するものであるとマーケットから信認を得ることが大事だ」と語り、規制のもとで実績を積んでいった上で新しいマーケットを形成する必要性を強調した。