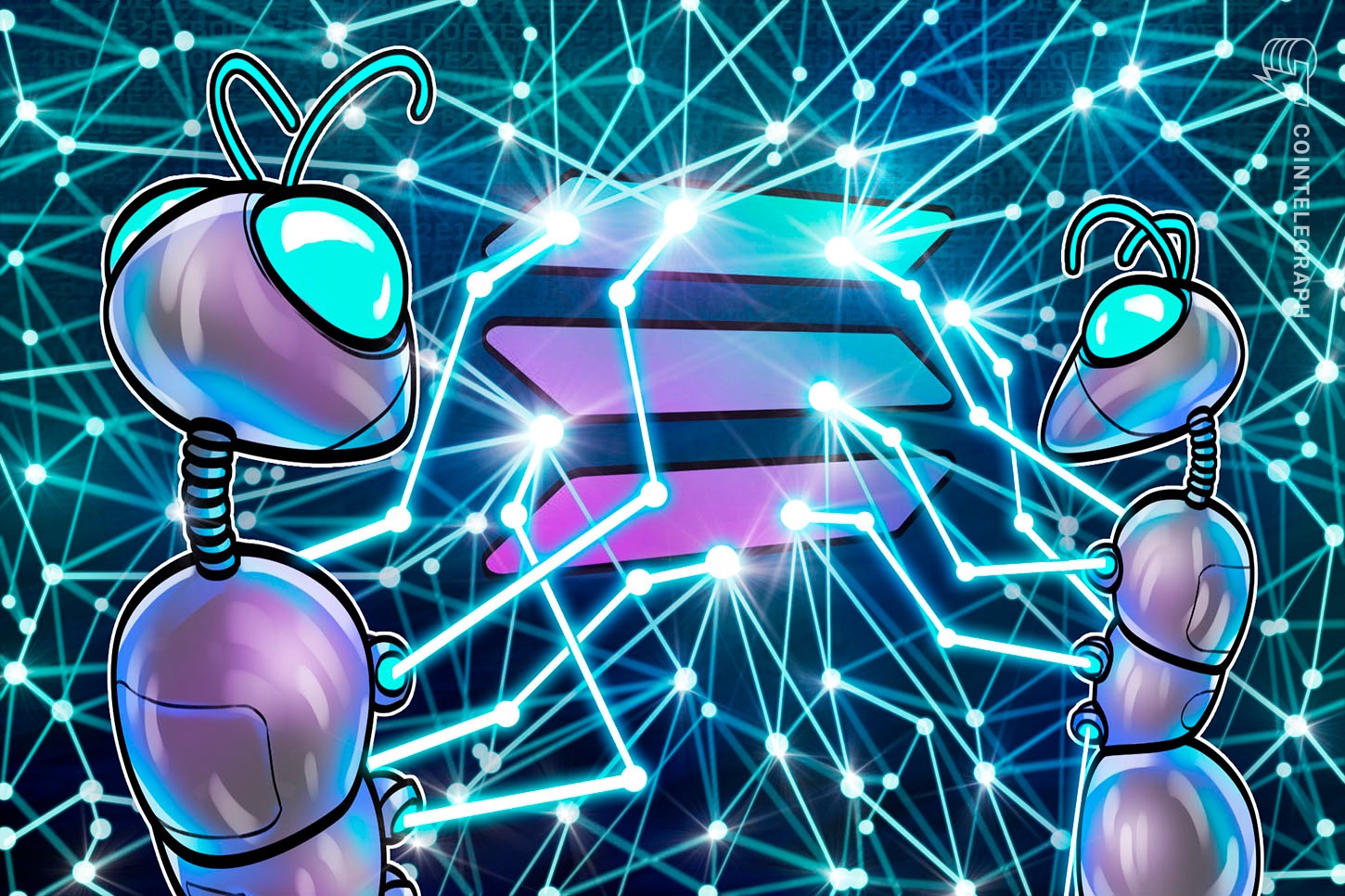ブロックチェーン「Solana(ソラナ)」とは
Solana(ソラナ)は、ビットコインやイーサリアムと同じパブリックブロックチェーンの1つだ。パブリックブロックチェーン特有のネイティブトークン(仮想通貨)「SOL」を持ち、ネットワークのセキュリティ性能を高めるステーキングの仕組みも存在する。
SOLの新規発行に伴うインフレ率は、1年目の8%を基準に毎年15%下落する仕組みだ。ステーキング報酬として使用することやネットワークへの攻撃コストを高めることを目的に、最終的には1.5%に固定される。
ソラナのステーキングは、執筆時点(2021年5月)で11.72%ものAPY(Annual Percentage Yield、年間利回り)が出ており、600以上のバリデータがネットワークに参加している。
ソラナは、CやC++、Rustをはじめとして多くのプログラミング言語に対応している。柔軟性の高いバーチャルマシンの開発が進められ、今後も多くのプログラミング言語に対応する予定だ。
Solanaの特徴、他のブロックチェーンとの違い

ソラナの特徴は、1秒間に5万トランザクションを処理できる高いスケーリング性能だ。ビットコインやイーサリアムなど一般的なパブリックブロックチェーンには、スケーラビリティ問題がある。
これは、プルーフオブワーク(PoW)の抱える問題でもあり、セカンドレイヤーなどによって対応が進められてきた。
ソラナは、独自のコンセンサスアルゴリズムであるプルーフオブヒストリー(Proof of History、PoH)を採用することで、セカンドレイヤーに頼ることなく高いスケーリング性能を実現している。これにより全てのトランザクションをオンチェーンで処理することができるのだ。
トランザクションをオンチェーンで処理できるということは、ネットワークの透明性が高いことを意味する。セカンドレイヤーのようなオフチェーンまたはサイドチェーンを使用する場合、全てのトランザクションをオンチェーンで処理することはできない。つまり、ブロックチェーンの特徴である透明性を高い水準で維持できないのだ。
ソラナは、全てのトランザクションをオンチェーンで処理しつつ、秒間5万トランザクションを処理する高いスケーリング性能を実現することに成功した。トランザクション手数料も、ビットコインやイーサリアムと比べて非常に安価に抑えることができている。加えて、0.4秒に1回ブロックが生成されている点も特徴的だ。
ブロック生成の間隔が短いことは、ブロックチェーンの耐改ざん性が高まることにつながる。なぜなら、ブロックの生成はブロックのファイナライズが行われることを意味し、これが即時行われるということはそれだけトランザクションが覆る可能性が小さくなるからだ。
ソラナは、高いスケーリング性能を実現しつつ、ネットワークの分散性を維持することにも注力している。SOLトークンの保有者によるガバナンス投票を経て、SOLトークンのステーキングが導入されると、現在までに600を超えるバリデータがソラナネットワークでアクティブに活動するようになった。
ソラナのステーキングには、SolFlareというステーキング機能をサポートするウォレットを使用することで参加できる。ソラナにおけるステーキングの多数がSolFlare経由となっている。

出所:Solflare.com
Solanaにおける8つのコアイノベーション
ソラナは、8つのコアイノベーションを中心に高いスケーリング性能が実現されている。一般的に、パブリックブロックチェーンには「スケーラビリティ」「セキュリティ」「分散性」のトリレンマが存在する。
トリレンマとは、3つの要素を同時には実現できない事象を表す言葉だ。パブリックブロックチェーンの場合、例えば高いスケーラビリティを実現するには分散性を犠牲にしなければならず、逆に分散性を高めるにはスケーラビリティを犠牲にしなければならない。分散性が低いことはセキュリティにも影響する。
しかしながらソラナは、次の8つのコアイノベーションによってパブリックブロックチェーンのトリレンマを解消することに成功している。
- PoH(プルーフオブヒストリー):独自のコンセンサスアルゴリズム
- Tower BFT:PBFT(Practical Byzantine Fault Tolerance、ビザンチン将軍問題への耐性)をプルーフオブヒストリーに最適化
- Turbine:ソラナブロックチェーンへのデータ伝播プロトコル
- Gulf Stream:メモプール不要のトランザクション転送プロトコル
- Sealevel:世界初のスマートコントラクト並列処理
- Pipeline:トランザクションを検証するためのプロセッサをユニット化
- Cloudbreak : 水平スケーリングアカウント型データベース
- Archivers : 分散台帳ストレージ
中でも特徴的なのが、独自のコンセンサスアルゴリズムであるプルーフオブヒストリーだ。
プルーフオブヒストリーでは、一般的なブロックチェーンが使用しているタイムスタンプの代わりに、特定の時点でイベントが発生したことを証明する履歴レコードを使用する。
ソラナは、ビットコインと類似したブロック構造をしており、直前のブロックの出力値を次のブロックの入力値として使用し、次のブロックが生成されたことを直前のブロックが生成された直後であることの証明として使用している。

出所:ソラナのブログ
 ビットコインの場合、ブロックの確定(ファイナライズ)には毎回約10分の時間を要しており、その間はトランザクションが承認されていない状態となっている。これは、確率論的なアプローチを取っていることに起因しており、6つのブロックが生成された時点でようやくブロックチェーンが改ざんされないであろうとみなしている。
ビットコインの場合、ブロックの確定(ファイナライズ)には毎回約10分の時間を要しており、その間はトランザクションが承認されていない状態となっている。これは、確率論的なアプローチを取っていることに起因しており、6つのブロックが生成された時点でようやくブロックチェーンが改ざんされないであろうとみなしている。
つまり逆を言うと、6つのブロック(10分×6ブロック=60分間)が生成されるまではビットコインのブロックチェーンは改ざんされる可能性が高い状態で存在していることになる。ソラナは高いスケーリング性能を実現しつつ、ブロックの即時生成を認めることで同時にセキュリティを高めることにも成功したのだ。
Solanaのユースケース
ソラナは、そのエコシステムの大きさも特徴だ。DeFiをはじめとするブロックチェーンの活用事例の多くは、基本的にイーサリアム上で展開されていた。
しかしながら、イーサリアムの需要が高まるにつれてトランザクション処理が追いつかなくなり、次第にイーサリアム以外のパブリックブロックチェーンの勢力が拡大してきている。
ソラナはその筆頭格として2020年にローンチされ、現在までに100以上のプロジェクトがソラナに対応済みだ。具体的には次のようなプロジェクトがあげられる。
- セラム(Serum、SRM):分散型取引所(DEX)
- レイディウム(Raydium、RAY):分散型取引所(DEX)
- チェーンリンク(Chainlink、LINK):分散型オラクルプラットフォーム
- テザー(USDT):ステーブルコイン
- USDコイン(USDC):ステーブルコイン
- テラ(Terra、UST):ステーブルコイン
- ソルスターター(Solstarter、SOS):IDO(Initial DEX Offering)プラットフォーム
- ザ・グラフ(The Graph、GRT):分散型インデックスプロトコル
- アーウィーブ(Arweave、AR):分散型データストレージ
- シビック(Civic、CVC):ウォレットプロバイダ
テザーやUSDコインなど、多くの主要なステーブルコインが揃ってソラナへの対応を発表しており、急速にエコシステムを拡大している。またソラナ特有のプロジェクトとしては、分散型取引所(DEX)のセラムやレイディウムといったプロジェクトが人気だ。

出所:ソラナHP
分散型取引所(DEX)
ソラナ上で稼働しているDEXの代表例として、レイディウムが注目を集めている。レイディウムは、オンチェーンのオーダーブックに紐づけられた形でトークンの交換が可能だ。もう1つの代表例であるセラムのオーダーフローを活用するだけでなく、独自のプールを用意することで流動性をエコシステム全体に供給できる。
ソラナは、イーサリアムなどの一般的なパブリックブロックチェーンと比べて圧倒的なスケーリング性能を誇る。そのため、一般的なスケーリング性能では実現できないDEXでの指値注文やオーダーブックが可能となるのだ。
これはユーザーの利便性を高めることにも繋がるため、結果的にDEXの更なる台頭を後押しする材料となっている。
ステーブルコイン
ソラナの大きな特徴の1つとして、多くのステーブルコインをサポートしている点があげられる。テザーやUSDコインをはじめ、テラが流通しているのが特徴だ。
ステーブルコインが多く流通しているということは、それだけ多くの資金が流入しているということを意味する。テザーとテラは共に中国を中心にアジアで多くのシェアを持つステーブルコインだ。一方のUSDコインは、欧米を中心に多くのシェアを持っている。
つまり、ソラナは全世界で幅広く活用されているパブリックブロックチェーンであるということだ。イーサリアム上に展開されているDeFi市場では、テザーやテラはそこまで多くのシェアを有しておらず、これらの資金はソラナを中心に流入していることになるだろう。
Solanaの現状と今後
ソラナは、高いスケーリング性能を武器に2020年のローンチ後わずか1年未満で急速にエコシステムを拡大してきた。一方で、ローンチ後まだ期間が浅いこともあり使い勝手にはまだまだ課題が残されている。
しかしながら、使い勝手の悪さはソラナに限らずブロックチェーン業界全体の課題として認識されているため、時間の経過と共に確実に改善されていくことが予想できるだろう。
ソラナは既に100以上のプロジェクトをサポートしており、今後もその数は増加していくと考えられる。中でも、イーサリアム上に展開していたプロジェクトがソラナに移行または対応するケースが増えているのだ。
こういった傾向を踏まえ、ソラナはCertus Oneと提携することでWarmholeというイーサリアムとのブリッジ機能を開発した。これにより、イーサリアム上に展開されているプロジェクトが容易にソラナに対応することができるようになっている。
昨今は、ソラナ以外にもAvalanche(アバランチ)やCelo(セロ)などがイーサリアムとの互換性を実現しているが、ソラナはイーサリアム以外にも互換性を持たせている点が特徴だ。
分散型インデックスプロトコルのThe Graphとの提携では、APIを通した利便性の高いインデックスプラットフォームの開発も発表されている。これにより、ソラナ上に展開されているプロジェクトは、The Graphの提供するインデックスをプロジェクトに組み込むことができるようになる予定だ。
このように、ソラナは急速にパートナーを増やすことでエコシステムを成長させ、ユーザーに対して高い利便性を安価な手数料で提供しているのだ。現在開発が進められているイーサリアム2.0の進捗次第では、ソラナがパブリックブロックチェーンの長期的なシェアを拡大させる可能性も十分に考えられるだろう。
【関連記事】
ブロックチェーンとは|仕組みや技術、種類など解説