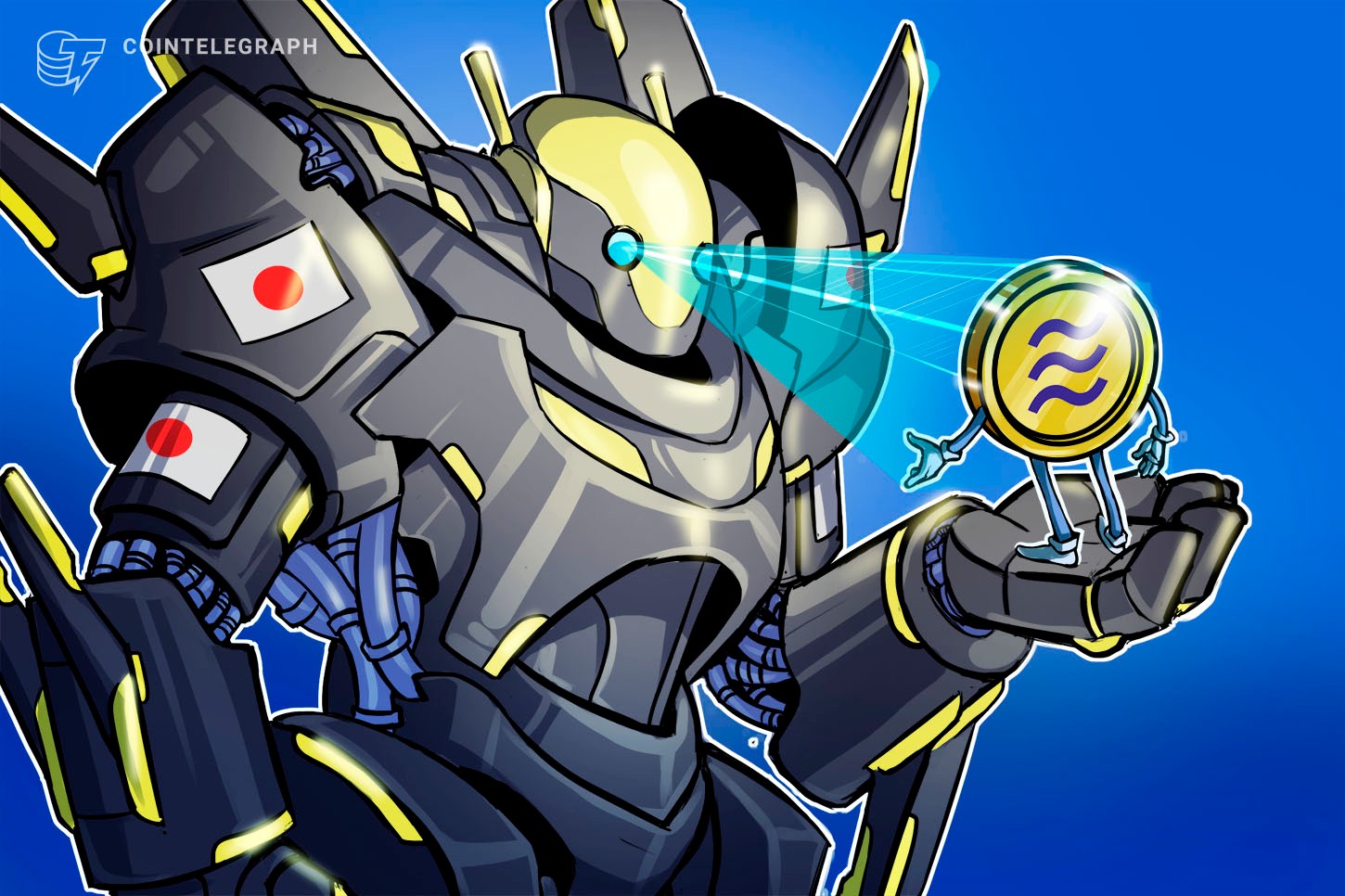日本銀行で決済機構局長を務めた山岡浩巳氏は、フェイスブックの独自仮想通貨リブラが広く普及すれば「金融政策の有効性を著しく低下させる」恐れがあると分析する。ロイターの2日付記事の中で指摘した。一方、元日銀政策委員の木内登英氏はリブラの規制について「中国がヒントになる」との記事を発表している。
新興国で「リブラ化」の恐れ
山岡氏は、政府への信認の違いによって、リブラのインパクトは異なると分析する。「(ドルや円など)信認の高い通貨を持っている国は、あまり恐れる必要がない」とするが、通貨への信認が低い国では「ドル化」ではなく、「リブラ化」が起こるかもしれないと語る。
「ドル化」とは自国通貨の代わりにドルが使われる現象だ。つまり「リブラ化」というのは、自国通貨の代わりに人々がリブラを使うようになるということだ。
山岡氏は、こうした「リブラ化」が起これば、「金融政策の有効性が著しく低下する」と指摘した。
リブラを「止めることはできない」
ブルームバーグの7月31日のインタビュー記事では、山岡氏はリブラにポジティブな評価も行っている。リブラの利便性は「圧倒的」であり、金融弱者を救おうとする動きを「止めることは難しいし、止めるべきでもない」と発言している。
また山岡氏は、リブラ実用化について2020年前半は難しいが、「今後2年程度で実現する可能性は高い」と予想している。
元日銀政策委員「リブラ規制のヒントは中国に」
別の元日銀関係者もリブラについて言及している。2012年から17年まで日銀政策委員を務めた木内登英氏だ。
木内氏は、野村総研に掲載された記事で「中国の施策がリブラ規制になる」と主張している。
中国ではアリペイ(支付宝)やウィーチャットペイ(微信支付)など、プラットフォーマーが決済サービスを提供している。
木内氏は中国がプラットフォーマーに対して、(1)決済プラットフォームが提供する投資商品に対する制限と、(2)決済プラットフォームに中央銀行の当座預金の保有を義務付けた点に着目。同様の規制をリブラの発行体となるリブラ協会に対して、同様の規制を行うことも選択肢になると主張している。
こういった規制により、「リブラの価値への信頼性、リブラの利用の安定を高める効果も期待できる」と木内氏は指摘する。
またアリペイやウィーチャットが、中国人民銀行の清算システムを通じて行っている点にも言及。リブラについても中央銀行の決済制度の中に組み込むという案も考えられるとしている。
編集・翻訳 コインテレグラフ日本版