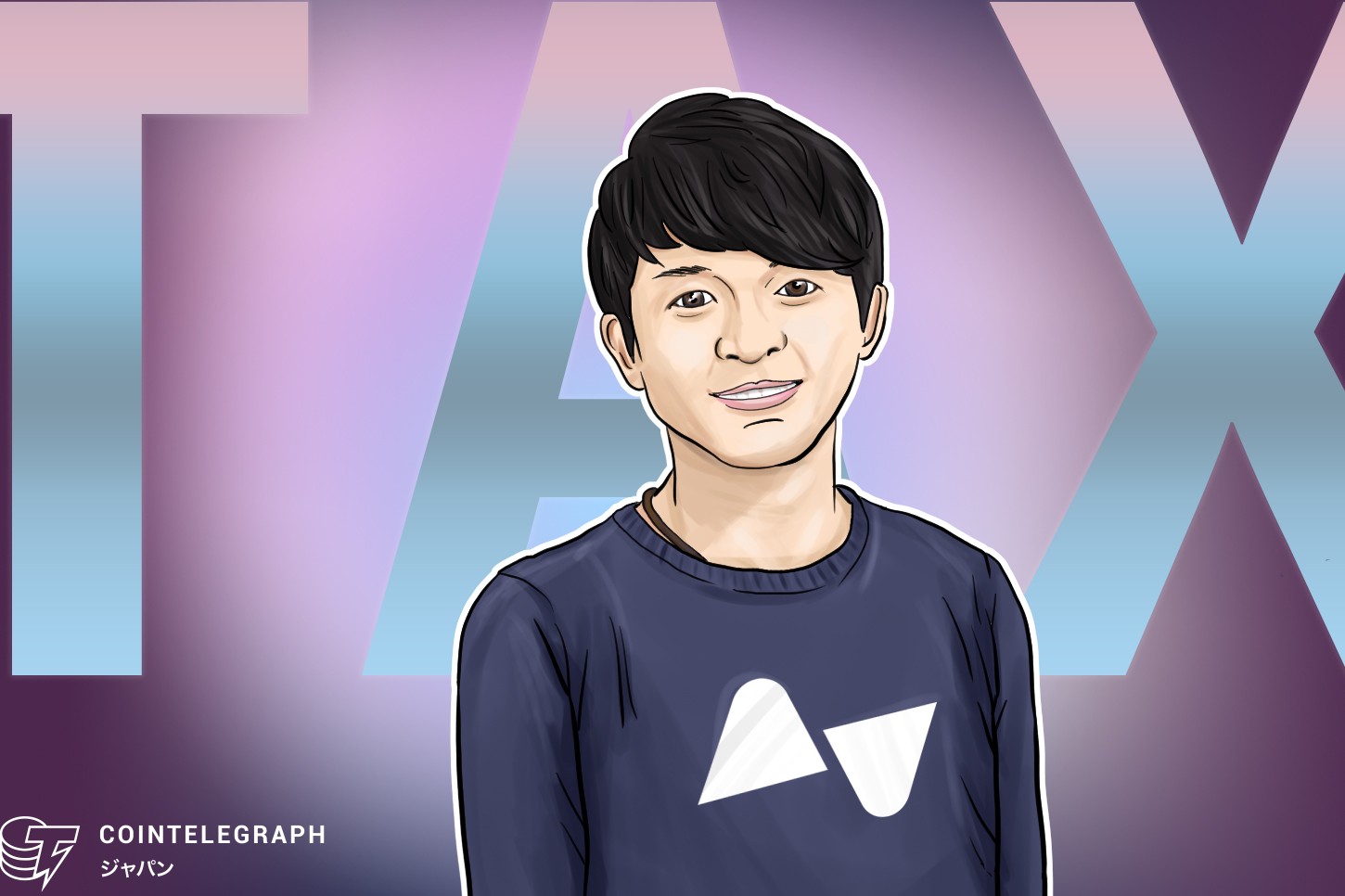仮想通貨取引で億単位を稼ぎ出した人の数は、確定申告時のデータによると昨年は331人だった。下落相場が続いている今年の仮想通貨市場からは、昨年のようには豊富に「億り人」が出てこないかもしれないが、今年もあと1カ月あまり、確定申告の時期は近づいてきている。
仮想通貨決済、マイニング、エアドロップ、詐欺だったICOトークン…仮想通貨に関する税処理は複雑で、専門家さえ頭を悩ませている。仮想通貨税計算ツール「Gtax」や仮想通貨税務に精通する税理士紹介サービス「ガーディアン」を展開している株式会社Aerial Partners(エアリアル・パートナーズ、東京・港)の代表取締役である沼澤健人氏は、今年は取引による儲けが少なく確定申告が必要ないと感じている人も、実は確定申告対象者である可能性があると話す。昨年は、日本で最も仮想通貨に関わる確定申告のサポートをしたという同社に、仮想通貨税計算に関する問題点や確定申告時の注意点などを聞いた。
仮想通貨取引で確定申告が必要になる場合は?
仮想通貨取引をしている人で、確定申告が必要になるのはどういう時か?簡単に言うと、会社勤めで給与所得を得ている人の場合、仮想通貨取引やその他副業で、1年間で20万円以上の利益を出している時だ。
仮想通貨取引による利益の計算は、「仮想通貨の売却(利確)」「仮想通貨による商品の購入」「仮想通貨同士の交換」など様々なタイミングで行う。利確だけでなく、商品の支払いや、仮想通貨同士の交換も所得計算の対象となるため注意が必要だ。
日本では、仮想通貨取引で得た利益は「雑所得」に分類される。雑所得には「総合課税」が適用される。給与所得などの計8つの所得を合算し、その所得総額に応じて税率が高くなる累進課税となる。税率は住民税と合わせて最大55%。給与所得などとは合算せずに利益に対して一律20%課税する「申告分離課税」の株式の売買やFXとは異なるので、この点も注意したい。また、申告分離課税の場合、損益を3年間繰り越せるが、仮想通貨の場合は、現状では繰越ができない。そのため、例えば昨年の損失分を今年の利益分から差引いて所得を計算することは出来ない点にも留意する必要がある。具体的な計算方法は、国税庁が11月21日に出した「仮想通貨に関する税務上の取り扱いについて(FAQ)」を参照されたい。
「今年は確定申告必要ない」は勘違い!? 総平均法の落とし穴
仮想通貨取引による所得の計算には「移動平均法」と「総平均法」の2種類が認められている。後者に関しては、翌年以降も継続して適用することを条件に例外的に認められている方法となっている。沼澤氏によると、仮想通貨元年と言われた昨年、初めて仮想通貨所得が実現し確定申告をした人の殆どが総平均法で計算した。昨年の右肩上がりの仮想通貨市場においては、1年間を通じて仮想通貨を売買した場合、移動平均法に比べると総平均法を使った方が、仮想通貨の取得単価が上がるため、計算される所得額が低くなりやすかったからだ。
しかし、当然ながら同じ仮想通貨取引をしている際に、計算方法によって所得金額が変わることはない。生涯の仮想通貨取引にかかる所得は、通算すると移動平均法をとっても総平均法をとっても同じになる。イメージとしては、総平均法では、2017年の含み益を2018年以降に繰り延べている状態だ。17年の仮想通貨市場は右肩上がりで、投資家の多くが利益を得ることができた。一方で、18年は下落相場に転じたことから、多くの投資家が体感的に確定申告の対象になっていないと感じているかもしれないと、沼澤社長は指摘する。
「実際、去年の前年同期の頃と比べると、単価として上がっている仮想通貨が圧倒的に多くて、かつ、総平均法で去年の所得を今年に繰り延べている状況なので、今年も(引き続き)仮想通貨取引をやられている方の多くが、所得が実現して、確定申告をしなきゃいけない状況に、実はなっている」
また、今年1月26日に発生したコインチェックのネム流出事件による補償は、日本円で支払われ、税処理上は保有していたネム(XEM)を売却し利確(もしくは損切り)したのと同様に扱われるため、実は利益を上げていて所得を実現していることに気がついていない人も多いと注意を促した。(円補償に関する国税庁の回答)
なぜ仮想通貨の税計算は難しい?
沼澤氏は、「感覚値ベース」と前置きした上で、昨年の仮想通貨取引による所得があり確定申告が必要な人のうち、実際に申告した人数は2〜3割くらいと感じていると話した。確定申告したいが仮想通貨の税計算方法が分からない、相談できる税理士がいない、などが理由と推測した。仮想通貨取引による所得計算が難しい理由について、沼澤氏は以下の3点を挙げた。
1、投資家が利用する仮想通貨取引所やウォレット数が多岐にわたるため
エアリアル・パートナーズが昨年、仮想通貨投資家の確定申告をサポートしたところ、投資家1人あたりが利用する取引所数は、海外取引所も含め平均6カ所ということが分かった。それぞれの取引所がそれぞれ異なるフォーマットで取引履歴を提供している、異なるタイムゾーンによる取引では仮想通貨取得時の計算が複雑になるなどの問題がある。これは株式取引やFXではみられない仮想通貨特有の問題となっている。
2、仮想通貨取引自体が日々進化しているため
仮想通貨取引に限らず、新しい技術や、それに紐付く新しい経済取引が出てきた際は、規制を整備するスピードが追い付かず、制度的な摩擦が生じる。マイニングによる報酬、イニシャル・コイン・オファリング(ICO)、セキュリティ・コイン・オファリング(STO)、今年で言えば、取引手数料マイニングやマーケティングの手法としてエアドロップが流行った。エアドロップでは、時価が付与時点で存在していない場合や時価がすでにある場合があり、また、個々の事例ごとに計算方法を確認する必要が出てくる。このように、仮想通貨を利用した新しい形態の取引が出てくると、現状ではその都度個別に対応をする必要がある。
3、仮想通貨同士の取引において円貨換算が複雑なため
仮想通貨同士の取引による利益の算出は、仮想通貨をそれぞれ一度日本円に換算して計算する必要がある。特に海外取引所において、法定通貨建てではなく、ビットコインやイーサリアムなどの仮想通貨を基軸通貨とした仮想通貨同士の交換が盛んだ。海外の取引所を使うと、円貨建ての時価情報が入ってこないため、その取引を円貨に換算する手間が入り計算が複雑になる。
単一の取引所での現物取引のみの場合、仮想通貨税の計算はツールを使えば複雑ではないだろう。しかし実際は、国税庁が提示した取りまとめで全て対応できるほど単純でない。株式やFXと異なり、仮想通貨取引は複数の取引所間で送金やトレードが可能であり、複数の取引所を利用し売買する場合が多い。
このような状況では、単一の取引所において損益計算レポートを取引所が出していても、全体を総合した時の所得の金額計算はひとっ飛びにはいかなくなる。取引所に入ってきた仮想通貨の取得原価が分からないため、源泉徴収して税金を取るのは仕組み上難しいという。また、確定申告は仮想通貨だけではなく、例えば、ふるさと納税や住宅ローン控除などその他の申告も入ってくるため、仮想通貨所得の計算ツールに加え、税理士に相談するのが安心だろう。沼澤氏は、国税庁が21日に公表した「仮想通貨の計算書」では、◆国外の仮想通貨取引所を利用している◆マイニング等の仮想通貨取引を行っている◆移動平均法を利用した所得の算定を行う――場合、対応が難しい印象があると話している。
確定申告を怠ると…
国税庁は、2017年の確定申告で、雑所得収入が1億円を超える人のうち、仮想通貨取引をしていた人の数が331人だったと明らかにしている。日経新聞によると、この331人という数字について、国税庁は「おおむね適正な申告がなされたのではないか」と言っているのに対し、仮想通貨の業界関係者は「昨年の高騰や広がりを踏まえると少なすぎるという印象」と話している。
億り人までは行かないまでも、確定申告は国民の義務であり怠れば罰則がある。最近では、仮想通貨取引による2017年のキャピタルゲインを申告していなかった米国の学生が、現在、40万ドルの税金を支払えずに窮地に陥っていると話題になった。アメリカの仮想通貨ニュースメディアであるCCNによると、同学生は、昨年5月に当時50ドルだったイーサリアムを5000ドル分を購入した。また、数種類のアルトコインやICOトークンにも投資した(仮想通貨同士の交換)。12月の仮想通貨市場の盛り上がり時には、含み益は約88万ドルに膨れ上がっていたが、のちにICOトークンの価値は急落。現在の学生のポートフォリオは12万5000ドルに縮小したという。学生は仮想通貨を一度も法定通貨に交換せず、また、仮想通貨同士の交換に税金がかかることを知らなかったと話している。
仮想通貨税制の未整備や、米国の学生のように制度自体を知らなかった場合でも、納税の義務は付いてまわる。日本でも、仮想通貨にかかる税金の計算方法が分からなかったといって申告せずにいるとトラブルに成り得る。確定申告の期限を過ぎた場合は、元々の納税額に加え、納付額の10〜15%の「無申告加算税」がかかる。また、納税期限を守らなかった場合には「延滞税」も課される。
「所得金額とか、仮想通貨売買頻度にほぼ関係なく、満遍なく税務調査が入っているという認識があるんですね。これくらいの所得でも調査が入ることがあるのかという場合も。[…] 確定申告している以上は、いつかはローテーションでまわってくることになっているので、明日は我が身と思っておいた方が良い(沼澤氏)」
確定申告を正しく行うために、事前に準備をしておくことが重要になると沼澤氏は指摘する。仮想通貨取引所によっては、限られた範囲の取引履歴しか取得できなかったり、取引所が閉鎖になってしまったりなどのトラブルは「よくある」という。その場合は、「一番安い時に買って、一番高い時に売ったという(想定をして)保守的な申告をしなくてはいけなくなる」可能性があるため、日頃から使っている取引所の取引履歴をこまめに取得しておくのが良いという。
今後の仮想通貨税制
沼澤氏によると、現在の仮想通貨税制は、FXの黎明期と同じような動きになっている。当時、FXを含む税務調査でペナルティを受けて破産者が続出していた。そのような負の歴史を繰り返さないために、脱税を働けないような規制を整備するのも大事だが、「確定申告したい方が、申告できない状況を解消することに主眼をおいてルールづくりをするべき」と沼澤氏は主張する。「FX時代の制度設計を上回るスピードで積極的な検討がされているとの認識はあるが、立法実務のスピードはあげられない」。しかし、制度の不備や分かりにくさを持って確定申告しない理由にはならない。
沼澤氏が参加する「暗号通貨に関する租税制度研究会」は今年4月、日本ブロックチェーン協会(JBA)と日本仮想通貨ビジネス協会(JCBA)に対し、仮想通貨税制の改正案を提出している。同研究会の作成した改正案の中で取引に関わる部分では◆仮想通貨同士の交換にかかる損益を一旦認識せず、法定通貨との交換時点もしくは支払い時点まで損益の繰り延べ可能とする◆仮想通貨による少額の決済時の非課税制度を導入する◆20%の申告分離課税の導入と損失の3年間繰越しを可能にする――等を提案した。
日本の仮想通貨税制が、例えば同研究会の提案通りに整備されれば、煩雑な税計算を理由とする仮想通貨決済の忌避解消や確定申告のハードルを下げるのに繋がるのはもちろん、仮想通貨市場への参加者の拡大、また、税処理にかかる時間の削減により仮想通貨関連事業の開発者が本来の開発に専念できるといったことも期待できる。仮想通貨税務に実際に関わっている現場からのこのような提案が政府レベルで議論されるのはいつになるのか。沼澤氏は、来年に審議する内容をまとめた今年の税制改正大綱(12月中旬頃には発表される見込み)では「仮想通貨に関する情報が1文入れば良いかなというレベル」と推測した。残念ながら、仮想通貨税制の整備にはまだまだ時間がかかりそうだ。
エアリアル・パートナーズとしては、仮想通貨の損益計算をシームレスにするために、制度というよりも、取引所やウォレット事業者に対しオープンAPI導入をまず呼びかけて行きたいという。損益計算は1ピースかけていても成立しなくなる。バイナンスなどの海外の取引所と異なり、国内の取引所ではAPIを公開していなかったり、していても情報が部分的であったりする。オープンAPI導入が進めば、自動で毎日損益結果が実現できる。税周りの制度的な摩擦を取り除き、仮想通貨・ブロックチェーンの社会実装促進を支援して行きたいと話した。
2018年(平成30年)の所得税の確定申告期間は、2019年2月18日~3月15日となっている。
【関連記事】
国税庁が「仮想通貨の計算書」を公表、税申告の簡便化につなげる狙い
コインテレグラフのLINE@アカウントができました!
— コインテレグラフ⚡仮想通貨ニュース (@JpCointelegraph) 2018年10月31日
毎日の仮想通貨ニュースまとめをLINEで配信してます!
こちらから登録してください!https://t.co/r9ZlA6PaWc pic.twitter.com/R9ovDWCw79