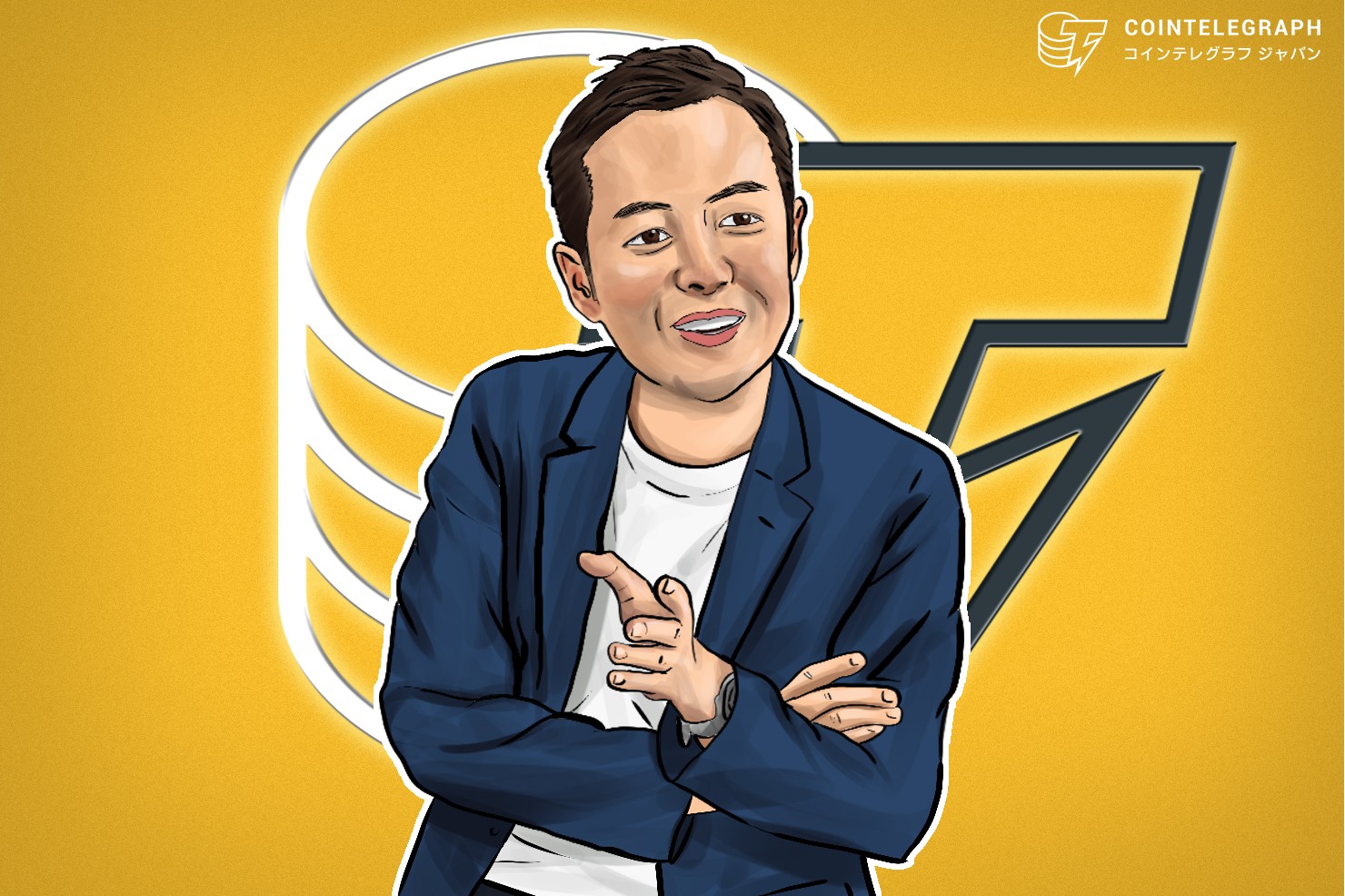働き方や企業の形が多様化する中で、企業の人事制度や福利厚生整備は追いついていない。一つの企業に長く勤める形が代わり、人材の流動性も高まっている。企業にとっても従業員の評価や採用時の情報収集など、課題が山積する。
こうした課題について、社内のコミュニティ活性化やボトムアップ式の評価手法を構想し、新しい企業の形を作ろうとしているのが社内仮想通貨の発行事業を手がけるコミュニティオの嶋田健作CEOだ。堀江貴文氏が社長を勤めていた当時にライブドアに参画。その後事業部長を務め、LINE子会社で社長にも就任した。
ITの全盛期を享受した嶋田氏が社内仮想通貨に取り組むのは何故なのか。社内仮想通貨を作るプラットフォームは企業の経済活動をどのように変えようとしているのか。6月6日にセレスとクロステックベンチャーズから1億円の資金調達をし、今後事業を拡大しようとしている嶋田氏に話を聞いた。
国、企業を超えて広がる経済活動
「経済が国を超えるような、大きな企業体ができてきた時に、その企業の社員のために通貨を発行する時代がくる。」
嶋田氏が代表を務めるコミュニティオは社内通貨や学内通貨として使えるコインを発行するプラットフォームを展開している。社内通貨だけでなく学内通貨や地域通貨、イベント限定の通貨などユースケースに合わせて柔軟に運用設計が可能なことをウリにする。
嶋田氏は今後、会社や地域の経済活動の流れが大きく変わっていくのではないかと予想して社内仮想通貨に取り組んでいる。特にGAFAなどは小国を超えるほどの財力を持つ。「世界的に人不足となる中で、特に大企業では自社の経済圏の中に従業員がジョインすることが指標になるのではないか」と予測する。社内だけに止まらず、国や単一の企業を超えた経済を見据え、社内仮想通貨の発行に取り組む。

仮想通貨の活用事例は欧州の有名ブランドやエネルギー企業など世界中で始まっているが、日本はまだまだ取り組みが少ない。嶋田氏はユースケースを考え、企業が抱える課題に仮想通貨が貢献できると考える。
「コミュニケーションの活性化などいい例ですが、企業も評価システムの構築に悩んでいます。実際に業務を頑張っているのに評価に繋がらなかったりすることは多い。企業にはボトムアップからの評価軸など、従来の評価とは異なるものが必要になってきています。これに仮想通貨が使えるのではないでしょうか。社内仮想通貨は会社の経済活動全体を活性化させるニーズを捕まえられるのです。」
評価システムが仮想通貨に紐付けば、秘密鍵の利用によって転職時に前の企業の評価を転職先の企業が知ることも技術的には可能になる。さらに有給休暇などの福利厚生も横断的に使えるようになるかもしれないという。就業や転職などでこうした情報を知りたいという企業は多いだろう。
嶋田氏自身、管理職や経営者としての経験から会社の人事制度構築で苦労した。
「経営側からしても頑張っている社員にどう還元するかは悩みどころです。グーグルなどが採用するOKR(企業全体から部署、チームの目標を管理する仕組み)のようなトップダウン式ではなく、会社の現場から評価制度を構築したいと考えました。社内仮想通貨のシステムができればボトムアップの新しいマネジメントの形が実現できるのではないかと思っています」
社内仮想通貨で会社をゲーム化する
社内仮想通貨という仕組みの発想について、コミュニティオの母体であるオルトプラスの事業が基になっているという。オルトプラスはソーシャルゲームなどを開発するゲーム会社だ。嶋田氏はこのオルトプラスで当初からR&D業務に従事していた。ゲーム会社ということもあり、「出社ボーナス」など参加型の評価システムなどを考案していたという。その流れで「会社のゲーム化」という発想に至った。
しかし、ゲーミフィケーションを取り入れるとしても事業や施策にどう繋がるのだろうか。「ゲームは毎日参加、ログインしてもらうことは重要。ゲーミフィケーションでは社員が毎日参加したいと思う仕組みを作った上で、会社側が参加してもらいたいと思う事業とは何かを考え、そこに仮想通貨使う」という。
「例えばコミュニティオでは出社した際に挨拶してくれるbotを作っています。曜日ごとに挨拶が変わり、社内一人ひとりにランダムに挨拶を変えています。会社に来ただけで褒められた気分になり、さらに自分だけできていなければ「悔しい」となり、会社にくるインセンティブになる。こうした仕組みを作った上で、社員にプレスリリースを拡散してもらう、リツイートしてもらう、もしくは採用に協力してもらうという『行動』をポイント化します。こうして「会社をゲーム化」したときの数値化に使えるものが社内仮想通貨です。こうして数値化すると、必要のないものにはお金が集まらなくなります。事業にとって必要のあるもの、ないものを明確にできます」
特に社内仮想通貨はマネジメントが重要な規模の大きい企業に有効だ。細かい評価が多くなったり、調整業務が必要なのに、お互いの顔が見えなくなったりしている企業から引き合いが多いという。
2000年のITバブルとブロックチェーンとの関係性
こうした取り組みについてライブドアなどの豊富な経験はどのようにつながっているのだろうか。嶋田氏自身は「システム開発の経験ぐらい」と素っ気ない。

現在のブロックチェーン、仮想通貨の盛り上がりは2000年代のITバブルの流れと酷似していると指摘する人もいる中で、嶋田氏は、
「当時はバブルが弾けて経済が停滞、膠着していましたが、当時と比べて今は資金調達がしやすくなりました。さらにテクノロジーを育む土壌ができてリスクマネーも市場に出回り、スタートアップが事業を始めやすいという大きな違いがあります。似ているというより、現在の方が良い環境になっています。ただ、法整備が追いついていないという点が同じと言えるのではないでしょうか」
こうした法整備の未熟な点についても「堀江さんが当時『電子書籍が絶対くる』と言っていてデータセンターを作っていましたが、10年以上経った今、これらはようやく普及しました。これと同じようにブロックチェーンも時間をかけて、浸透するのではないでしょうか。」と考える。嶋田氏のブロックチェーンへの期待感は大きい。
第三者に正当性を担保するブロックチェーンは、ビジネスモデルの大きな転換点となります。まだまだニーズも広がるでしょう。2000年代はソフトウェアによるところが大きかったですが、現在はサブスクリプションなどビジネスモデルが多様になってきています。1、2年でビジネスモデルはすぐに変わる状況になってきており、そうしたワクワク感があります。
嶋田氏は今後、さらなる事業の拡大を考える。セレスとクロステックベンチャーズから1億円を調達し、プロダクトのブラッシュアップを図る。多くの企業のユースケースに対応していくという。
文 Yoshihisa Takahashi
編集 コインテレグラフ日本版
本インタビューは、明確性を高めるために編集および要約されています。