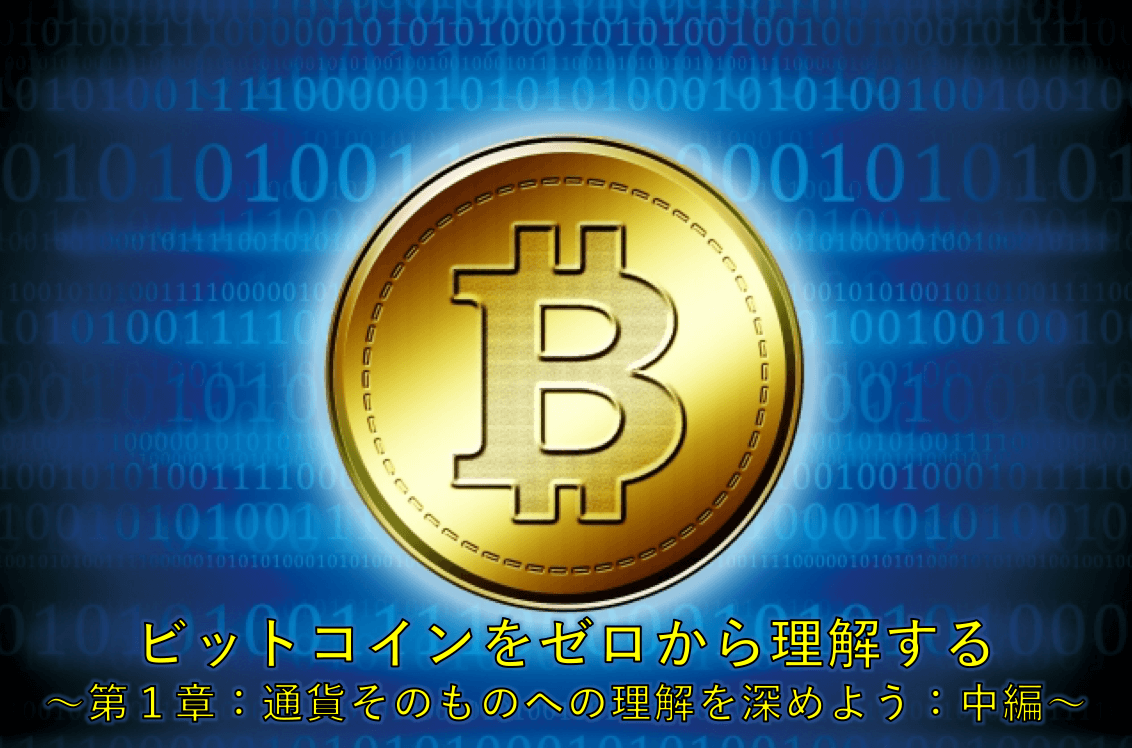前回の記事(前編:言葉の定義をはっきりさせよう〜通貨・貨幣・お金の意味〜)で、通貨・貨幣・お金という言葉の意味について整理した。では、いよいよ本章の本題。通貨・貨幣の機能は何か、そして貨幣がなぜ価値を持つのかについて言及していこう。
通貨・貨幣の機能
通貨・貨幣の果たしている機能については、様々な学者が整理している。ここでは代表的な役割について簡単に紹介しよう。
「価値尺度」機能
モノやサービスの価値を示す機能のこと。例えば日本であれば日本円があらゆるサービス・製品の価値をはかるものさしとなっている。(e.g.うまい棒=1本10円)「交換・決済手段」機能
モノやサービスを交換したり、それらの価値に対して報酬を支払う機能。これはおそらく一番わかりやすい機能であろう。私たちはものを買う際に対価としてお金を使用する。(e.g.一万円のメロンを買うために一万円札を使用する)「価値貯蔵手段」機能
価値を蓄積・保存する機能。いつまでも変わらずに価値の額面(がくめん)がある(100円はいつまでも100円)ので、価値を蓄積・保存できる。この機能も貯金を想像してもらえればわかりやすいだろう。
以上が通貨・貨幣の代表的な役割である。では次に、通貨・貨幣がなぜ価値を持つのかについて言及していこう。
通貨・貨幣が価値を持つ秘密とそれについての様々な意見
読者の方々も「なぜ通貨・貨幣が成立するのか?」という疑問を一度は感じたことがあるのではないだろうか。より卑近な例として、一万円札を例にとると、「ただの紙切れでしかない一万円札に、一万円という価値がやどり、モノやサービスの売買で使えるのは、なぜだろう?」という疑問である。筆者がこの疑問を抱いたきっかけはビットコインの存在であった。ビットコインは、言ってしまえば、データ・数字でしかなく、そこになぜ価値がやどっているのか全くわからなかった。この疑問を突き詰めていくと、普段使用している紙切れの一万円札がなぜ価値を持つのかわからなくなってくる。
通貨・貨幣が価値を持つ理由については様々なことが意見がある。
私自身が勉強していくなかで、もっとも納得感のあった説は、経済学者の岩井克人氏の「貨幣が価値を持ち貨幣として成立するのは、それが貨幣であるからだ」
(参考:「貨幣論」、「資本主義から市民主義へ」いずれも岩井克人著)という説である。
この説の詳細に入る前に、まずは通貨・貨幣の価値の根拠・源泉についての様々な意見を紹介しよう。
1.見た目の魅力が価値を担保している説
金・金貨が通貨・貨幣であった時代・場所において、金が通貨足り得たことへの説明として、金が万人にとって魅力的な輝きを持つからだという意見がある。金が魅力的な輝きを持っているというのは、古代エジプトで一部の特権層が装飾品として用い、富の象徴として金を保有していたことを思い返してもらえればわかるであろう。しかし、そもそも金や金貨が生来の性質として万人にとって価値を持つことを証明できない以上、適切だと判断することはできない。また、金との交換が国家によって保証されなくなった現代の不換紙幣(e.g.一万円札等)が価値を持つ理由も説明できない。
2.生産に投下したコストが価値を担保している説
資本論や共産党宣言で有名な19世紀を代表する経済学者であるマルクスは、通貨・貨幣の価値の源泉をそれを作り出すのに必要な労働力に求めた。
まず、彼は小麦や魚、リンネルといった、交換可能なあらゆる商品の価値の裏付けは労働力であると考えた。そのうえで、金という商品が、均質的で、分割可能で、耐久的であるという、貨幣として適した性質を持つことから貨幣として選ばれたのだと主張する。つまり通貨・貨幣の価値は、他の商品と同じく労働力にあるとした。ここでいう金であれば、採掘にかかる労働力であるということである。
この説は、ビットコインの価値をマイニングする際にかかるインフラ費用や電気代によるものとするという論に近いと言える。ビットコインの価値を支えているのが電気代であるという考えは、著名なビットコイナーである大石氏らが唱えるところである。
とはいえ、この説では紙幣(e.g.一万円札等)の存在をうまく説明できない。紙幣を作るのに投入するコストはあきらかにその紙幣が持つ価値よりも少ない。例えば、1万円札の製造コストは、1枚あたり約20円である。(参考:https://zuuonline.com/archives/115589/2)
3.通貨・貨幣がその他の価値あるものと交換できることを国家が保証している説
媒介物としての通貨・貨幣そのものに価値はないが、その他の価値あるものとの交換を国家が保証することによって価値が生まれるという説である。
歴史的に見ると、アメリカ・日本など各国における金本位制下の兌換紙幣(=国が金と交換できることを保証した紙幣)がその一例としてあげられるであろう。
しかし、この説も現代の不換紙幣(e.g.一万円札等)が価値を持つ理由を説明することはできない。日本においては、1988年に「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」が施行されてからは、金と紙幣との交換は国によって保証されていないというのが現状である。
さて、今まで様々な説を紹介してきたが、どれも筆者の納得のいく説ではなかった。
筆者は過去20年ほどお金を使いモノの購入等を行ってきたが、見た目の魅力・生産に投入されたコスト・国家による保証、いずれも意識したことがなかったためである。
そこで登場したのが岩井氏による、「貨幣が価値を持ち貨幣として成立するのは、それが貨幣であるからだ」という説なのである。その説明をしたいのだが、本編が長くなりすぎてしまったので、次回の後編にその説明を譲ることとしよう。
本記事のまとめ
通貨・貨幣の代表的な機能は以下の3つ
モノやサービスの価値を示す 「価値尺度」機能
モノやサービスを交換したりそれらの価値に対して報酬を支払う 「交換・決済手段」機能
価値を蓄積・保存する 「価値貯蔵手段」機能
貨幣の価値を支える根拠については様々意見があるがどれも不十分な点がある
次週、「貨幣が価値を持ち貨幣として成立するのは、それが貨幣であるからだ」という岩井説の説明を行う