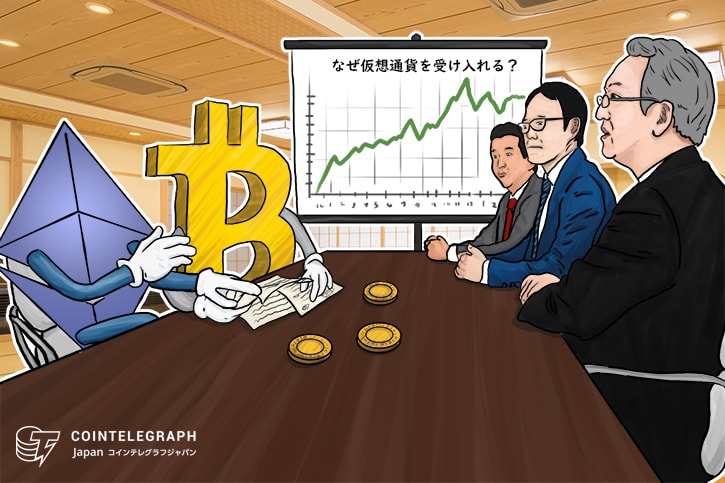金融庁は11月1日、仮想通貨交換業等に関する研究会の第8回の会合を開いた。会合では、イニシャル・コイン・オファリング(ICO)について、一定の類型を設けた上で適切な規制を設ける案などが議論された。
今回の議論は、スイスでの規制の事例を参考にし、いくつかの類型を設けた上で規制を進める考え方が紹介された。
スイスでは、①決済に使う「ペイメントトークン」、②特定のサービスやデバイスに使われる「ユーティリティトークン」、③配当や利子が得られるような「アセットトークン」に分類。ユーティリティトークンの一部やアセットトークンについては証券規制を適用している。
現在の日本の規制枠組みでも、特定の事業に対する収益分配兼の持分を販売する「集団投資スキーム」や、非上場の株式を販売する「株式投資型クラウドファンディング」といった仕組みがある。研究会のメンバーの中からは配当や利子が得られるようなICOについては、こういった規制枠組みの中で規制できるようにするべきといった意見が出た。

仮想通貨交換業等に関する研究会 第8回 金融庁参考資料より
ICO規制については、詐欺的な案件が横行している実態が指摘され、投資家保護の観点からも規制の必要性が多くのメンバーから出された。
またスタートアップの資金調達の新しい手段にもなりうるとの観点から、適切な規制を設けるべきとの声も出た。メンバーの中からは「現状は悪貨が良貨を駆逐するような状況で、いい業者が立ち行かなくなる」とし、悪質な業者を排除する仕組みづくりが重要だとの意見も出ていた。
ICO規制の議論は、一定の類型化のもとで規制をするべき意見が多く出たが、既存の枠組みの中で規制するのか、ICOに特化した規制枠組みを設けるのかなどは、今後の議論になりそうだ。メンバーの中からは、ICOの社会的意義についてより理解を深める必要があるとし、具体的なケーススタディをしていくべきとのアイデアも出された。