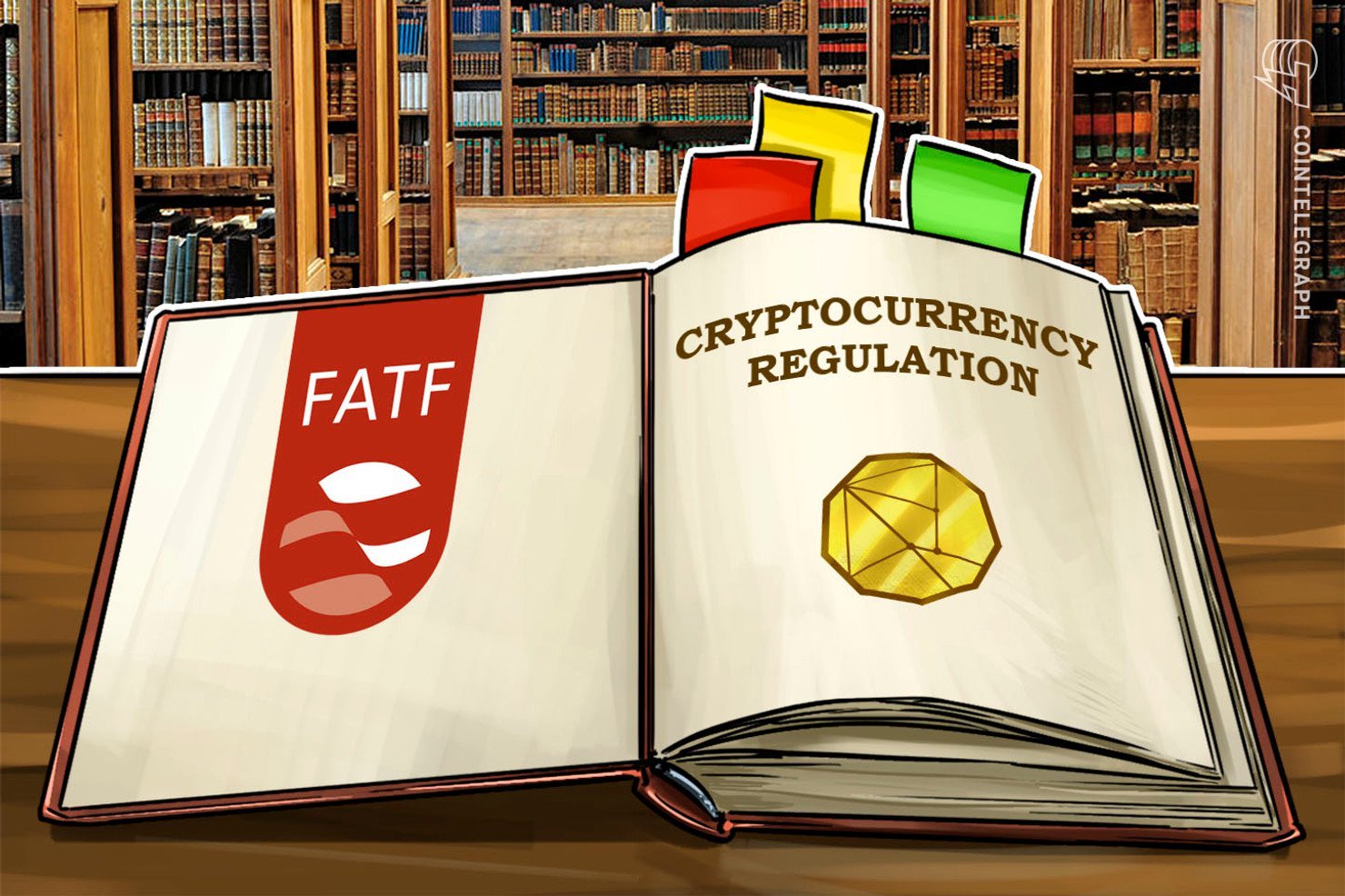アンダーソン・毛利・友常法律事務所のパートナー河合健弁護士は26日、日本仮想通貨ビジネス協会で講演し、このほど公表された金融活動作業部会(FATF)のマネーロンダリング対策の「解釈ノートとガイダンス」について「7bが大きな議論が呼んでいる」と注目点を強調した。7bを実際に適用するには技術的な問題があり、官民で協力して検証していく必要があるとした。
今回のFATF勧告15の解釈ノート8項目の概要について、1~6はすでに日本の事業者であれば対応できている項目であり、これらは国外の事業者が影響を受けるものだ。この8項目の中でも日本の事業者に大きな影響があるのが「7b」であると説明。ここには仕向・被仕向VASP(仮想通貨サービス業者)が取得すべき送付人、受取人情報などについて定義されている。
これについて河合弁護士は
- 一見取引での閾値はUSD/EUR1000である
- 仕向VASPが正確な必須送付人情報及び必須受取人情報を取得及び保持し、即時かつ安全に提出すること。被仕向VASPが必須送付人情報及び正確な必須受取人情報を取得及び保持し、規制当局の求めに応じて利用可能にすることを確保すべき
という点が留意すべき点だと強調した。つまり仕向VASPは送付人情報については正確性が要請され、被仕向VASPには受取人情報の正確性が要請されるという。
しかし、ここにも問題がある。
「例えば受取側のみが正確な情報を持っていて、送付元からの情報と異なる場合、宙に浮いてしまうトランザクションが出てくるのではないか」
と予想する。そしてこれについて解決策が見えていないことも危惧されるという。これを送り返すこともリスクも出てくるからだ。そしてこれらの個人情報は各国の個人情報保護法や、適切な対応できているのかわからない国に送ることが可能なのかなど、まだまだ課題は山積していることを挙げた。
最後にビジネスの全体的な影響について河合弁護士は
- 各国に免許制、登録制が導入されること
- KYC、CDD(カスタマーデューデリジェンス)の閾値が非常に低いこと
- 情報の伝達(正確な情報のやり取り)
の3点が課題になるという。このため、「規制が緩い地域で利益を得るモデルは転機を迎えるだろう」と指摘。そして投機的な資金は減っていくとの予測を示した。
「情報の伝達」については免許制度のない国には仮想通貨を送ることの自体に規制がかかる可能性があり、そのためピアツーピア(P2P)取引が増加することになるかもしれないと話した。