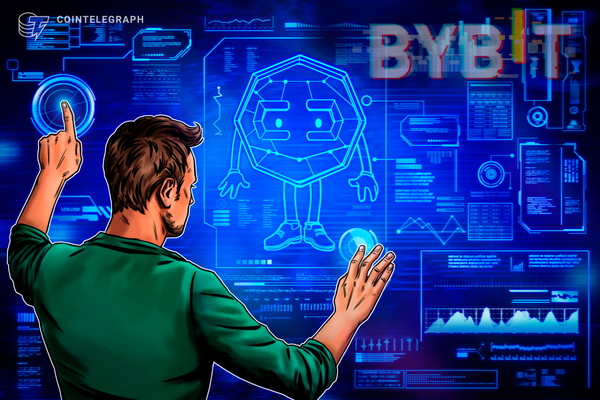Bybitで仮想通貨取引を行って大きな利益を得たものの、最大55%にもなる税負担の重さに悩んでいませんか?その有効な対策として注目されているのが、法人を設立し「法人口座」で取引を行う方法です。
この記事では、Bybitで法人口座を開設する具体的な手順や必要書類を、初心者の方にもわかりやすく解説します。さらに、個人口座との違いや、法人化による税務上のメリット・デメリットについても詳しくご紹介します。
この記事を最後まで読めば、法人化すべきかどうかが明確になり、迷わず手続きを進めることが可能です。
Bybit(バイビット)で法人口座の開設は可能?
仮想通貨取引による利益の節税や、会社の資産運用の一環として、Bybitの利用を検討する法人が増えています。多くの会社経営者や個人事業主が抱く「Bybitで法人口座は作れるのか?」という疑問に、本セクションで明確に答えていきます。
法人としてBybitを利用するための仕組みや、なぜ特別な本人確認手続きが求められるのか、その理由について詳しく見ていきましょう。
法人名義でのアカウント作成と法人KYC(本人確認)で対応
結論として、Bybitで法人口座を開設することは可能です。ただし、Bybitには「法人口座」という専用のプランが用意されているわけではありません。
まず個人口座と同じようにアカウントを登録し、その後に法人向けの本人確認(法人KYC)を完了させることで、法人口座として利用できるようになります。この法人KYCの手続きでは、会社の登記簿謄本や株主名簿といった、個人口座の開設時には不要な書類の提出が求められます。
すべての手続きが完了すれば、法人名義での入出金や取引が可能となり、実質的な法人口座として運用できる仕組みです。
法人KYCが必要な理由
Bybitで法人口座を利用するには、法人KYC(本人確認)の完了が必須。これは、国際的な要請に基づき、取引所の信頼性と安全性を確保するために不可欠な手続きとされています。
主な理由は以下の通りです。
金融犯罪の防止(マネーロンダリング)
法令遵守(コンプライアンス)
取引の安全性向上
全機能・サービスの利用
Bybitは顧客の身元を正確に把握することで、マネーロンダリングやテロ資金供与といった不正な資金の流れを未然に防ぎ、法令を遵守した健全な取引環境を維持しています。
また、ユーザー側にもメリットがあり、KYCを完了させると出金上限額が引き上げられます。万が一アカウントにアクセスできなくなった際の復旧もスムーズになるほか、Bybitが提供する全てのサービスやキャンペーンを利用するためにも、KYCは欠かせない手続きなのです。
Bybitの法人口座と個人口座の違い
Bybitを法人で利用する上で、個人口座との違いを正確に理解しておくことは極めて重要です。特に「税金の仕組み」「損失の扱い」「経費計上の範囲」の3点で大きな違いがあり、これらが法人化のメリットに直結します。
主な違いを以下の表にまとめました。
表の通り、最も大きな違いは税制面です。個人の利益は他の給与所得などと合算されて税率が決まるため、最大で約55%(住民税含む)の高い税率が課される可能性があります。
対して法人は法人税率が適用されるほか、損失を最大10年間繰り越せる「繰越控除」や、他の事業の黒字と相殺できる「損益通算」が認められています。これにより、長期的かつ戦略的な税務対策が可能になる点が最大のメリットと言えるでしょう。
Bybitで法人口座を開設するメリット
前のセクションでは、個人口座と法人口座の主な違いについて見てきました。本セクションでは、それらの違いが具体的にどのようなメリットをもたらすのかを、一つずつ詳しく掘り下げていきます。
法人化がもたらす「税率」「損失の繰越」「損益通算」「経費計上」という4つの税務上の優位性を正しく理解することで、最適な資産運用戦略を立てることが可能です。
①仮想通貨の利益にかかる税率を大幅に抑えられる可能性がある
法人口座を利用する最大のメリットは、利益にかかる税率を大幅に抑えられる可能性がある点です。
個人が仮想通貨取引で得た利益は「雑所得」として扱われ、給与所得など他の所得と合算した金額に対して課税されます。この総合課税では、所得が増えるほど税率も高くなる累進課税が適用され、住民税と合わせると最大で約55%もの高い税率が課されることになるのです。
一方、法人の場合は法人税率が適用されます。国税である法人税・地方法人税に加え、地方税の法人住民税・事業税をすべて含めた実質的な税負担率(実効税率)は、法人の規模や所在地によって異なりますが、最大でも34%程度に留まります。
そのため、仮想通貨取引で得た利益が大きいほど、個人で納税するよりも法人として納税する方が、手元に残る資金を多くできる可能性が高いのです。
以下の表は、個人の所得金額ごとの所得税率です。これによると、年間所得1,800万円以上は法人化したほうが税率が低いことがわかります。
【個人】所得税率
引用:国税庁
②損失を最大10年間繰り越せる(繰越控除)
法人化による税務上の大きな利点として、損失を翌年以降に繰り越せる「欠損金の繰越控除」制度の活用が挙げられます。これは、青色申告法人である場合に、ある事業年度で生じた純損失(赤字)を、翌事業年度以降、最大10年間にわたって繰り越し、将来発生した所得(黒字)から差し引くことができる制度です。
一方、個人の仮想通貨取引で生じた損失は雑所得に分類され、他の所得との損益通算はできず、損失を翌年以降に繰り越すことも原則として認められていません。
価格変動の激しい仮想通貨市場では、年によっては大きな損失を計上することも考えられます。そのような場合でも、法人口座であれば将来の利益と相殺して課税所得を圧縮できるため、長期的な視点で安定した事業運営が可能となるのです。
③他の事業所得と損益を合算できる(損益通算)
複数の事業を運営している法人にとって、損益通算が可能である点は大きなメリットとなります。損益通算とは、ある事業で生じた利益と、別の事業で生じた損失を、同じ事業年度内で相殺できる税務上の仕組みです。
例えば、本業であるコンサルティング事業で1000万円の利益が出た一方、資産運用として行っていた仮想通貨取引で300万円の損失が出たとしましょう。この場合、両者を相殺して、その年度の課税所得を700万円に圧縮することができます。
このように、法人であれば仮想通貨取引の損失を他の事業の利益と合算し、法人全体の税負担を軽減することが可能です。個人の場合は、仮想通貨の損失を給与所得など他の所得と相殺することはできないため、これは法人ならではの特権と言えるでしょう。
④経費として認められる範囲が広がる
経費として認められる費用の範囲が広がることも、法人化の大きなメリットです。個人の場合、取引に「直接」必要と認められる費用しか経費にできないのに対し、法人であればより広い範囲の費用を損金として算入できます。
法人で経費計上できる費目の具体例は以下の通りです。
取引手数料
PC・モニターなどの機材費
事務所の家賃・水道光熱費
インターネット回線費
情報収集のための書籍・セミナー代
役員・従業員への給与
税理士への顧問料
個人の雑所得では、取引手数料や一部の書籍代など、限定的な費用しか経費として認められていません。しかし法人であれば、上記のように事業運営に関連する幅広い費用を経費として計上できます。
これらを損金として計上することで、課税対象となる所得を圧縮し、結果的に税負担を軽減する効果が期待できるのです。
Bybitで法人口座を開設するデメリット・注意点
これまで見てきたように、Bybitの法人口座には税務上の大きなメリットが存在しますが、その一方で、個人口座にはないデメリットや注意点もいくつか存在します。安易に法人化を進めると、かえって負担が増える可能性もあるため注意が必要です。
本セクションでは、特に重要な「法人の設立・維持コスト」「資産の流動性の低下」「含み益への課税」という3つのデメリットについて、具体的に解説していきます。
①法人の設立と維持にコストがかかる
法人口座の開設自体は無料ですが、その前提となる法人自体の設立と維持には相応のコストが発生します。
まず、法人を設立する際には、株式会社であれば最低でも約20万円、合同会社でも約6万円の登録免許税や定款認証手数料といった初期費用が必要となります。さらに、法人を維持していくためのランニングコストも無視できません。たとえ仮想通貨取引で利益が出ていない赤字の状態であっても、法人住民税の均等割として最低でも年間約7万円の税金を納める義務があります。これに加えて、複雑な法人税の申告を税理士に依頼すれば、その顧問料も発生するでしょう。
これらの設立・維持コストが、法人化によって得られる節税メリットを上回るかどうか、事前に慎重なシミュレーションを行うことが不可欠です。
②利益を自由に使えず、資産の流動性が落ちる
法人口座で得た利益は、個人の資産とは明確に区別して管理しなければなりません。これは法人口座の大きなデメリットであり、資産の流動性が著しく低下する要因となります。
個人口座であれば、得た利益はいつでも好きな時に引き出して私的に利用できます。しかし、法人の資産はあくまで会社のものであり、代表者個人が自由に使えるわけではありません。法人の資金を個人が使うためには、役員報酬や配当といった正式な手続きを踏む必要があるのです。
法人の資金を私的に流用することは、業務上横領などの重大なコンプライアンス違反に問われる可能性があるため、厳格な資金管理が求められる点を肝に銘じておくべきでしょう。
③含み益にも課税される可能性がある
法人が仮想通貨を保有する場合、個人とは決定的に異なる税務上の注意点が存在します。それが「含み益への課税」です。
個人の場合、仮想通貨を売却または使用して利益が確定した時点ではじめて課税対象となります。しかし、法人の場合は、期末(決算日)時点で保有している仮想通貨を時価評価し、取得時の価格との差額(含み益)をその期の利益として計上し、課税対象としなければならないのが原則です。
仮想通貨の価格が急騰した期末には、納税資金を確保するために、保有する仮想通貨の一部を売却する必要に迫られる可能性もあるため、特に注意が必要です。
法人口座の開設に必要な書類と通過しやすくするポイント
Bybitで法人口座を開設する場合、個人口座の開設時とは異なり、法務局で取得する公的な証明書など、準備に時間を要する書類も必要になります。ここでは、法人KYCで求められる具体的な書類を一覧で示すとともに、審査を一度で通過するためのポイントも併せて解説します。
必須書類一覧(履歴事項全部証明書、身分証明書など)
Bybitの法人KYCでは、主に法人の実在性と事業内容、そして実質的支配者を確認するための書類が求められます。事前に以下の書類をデータ(PDFや画像ファイル)で準備しておくと、手続きがスムーズに進むのでおすすめです。
法人KYCに必要な書類リスト
法人設立証明書(登記簿謄本)
定款
最新の株主名簿
最新の役員名簿
会社の全役員情報(氏名、国籍、本人確認書類)
企業利益の25%以上を保有する最終受益者の情報
会社の組織図
法人の登記情報が記載された「登記簿謄本(履歴事項全部証明書)」は、法務局で取得する必要があり、発行日から3ヶ月以内のものが必要となります。
また、役員や最終受益者(実質的支配者)の情報として、各個人の本人確認書類の提出も必要です。株主名簿と合わせて、誰が最終的な意思決定権を持つのかを明確にするための重要な書類となります。
審査に通りやすくするためのポイント
法人KYC審査を一度でスムーズに通過するためには、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。
特に注意すべきは以下の3点です。
入力情報と提出書類の完全一致
各種書類の有効期限の遵守
鮮明で高解像度な画像データの準備
申請フォームに入力する法人名や所在地は、登記簿謄本などの公的書類と一字一句違わぬように正確に入力しなければなりません。また、登記簿謄本や住所確認書類には、発行後3ヶ月以内といった有効期限が定められているため、事前に確認が必要です。
提出する書類の画像データは、文字が潰れたり光が反射したりせず、四隅まで鮮明に写っているものを準備することが、審査を迅速に進めるための鍵となります。
【3ステップ】Bybit法人口座の開設方法とKYC手順
STEP1:法人口座開設に必要な書類を準備する
Bybitの法人口座開設は、法人KYCに必要な書類をすべて揃えることから始まります。スムーズな申請のために、事前に以下の書類をデータで準備しておくことが肝心です。
法人設立証明書(登記簿謄本)
定款
最新の株主名簿
最新の役員名簿
企業利益の25%以上を保有する最終受益者の情報
会社の全役員情報(氏名、国籍、本人確認書類)
会社の組織図
これらの書類は、法人の実在性や誰が実質的な支配者であるかを証明するために不可欠です。特に法人設立証明書(登記簿謄本)は法務局での取得が必要なため、早めに手配しておきましょう。
STEP2:Bybitの公式サイトでアカウントを登録する
必要書類が準備できたら、次にBybitの公式サイトから、次の手順でアカウント登録をします。
Bybitの公式サイトに行き、右上のメニューボタンをクリック
登録ボタンをクリック
「メールアドレス」と「パスワード」を設定する
メールアドレス以外にも、電話番号やGoogleアカウントやAppleIDでも登録可能です。
必要な情報を入力したら「入会特典をゲット」をクリックしましょう。
メールアドレス認証をする
「入金特典をゲット」をタップしたら、登録したメールアドレスに認証リンクが送られてくるので、認証コードをコピーして認証を完了させます。
以上でBybitのアカウント登録は完了です。
STEP3:アカウント情報から法人KYC(本人確認)に進む
Bybitのアカウント登録が完了したら、次に以下の手順で「法人KYC(本人確認)」に進みます。Bybitには法人口座といったプランは無いが、この法人KYCを完了することで、実質的に法人口座として利用することが可能です。
アカウントボタンから「アカウント」をタップ
「本人確認(KYC)を行う」ボタンをクリック
「法人確認」ボタンをクリック
「本人確認(KYC)を行う」ボタンをクリック
会社の基本情報を入力する
ここでは、以下の会社の基本情報を入力します。
会社名
登記上の会社名(任意)
法人設立地(国・地域)
メイン事業拠点
登録事務所
会社のウェブサイト(任意)
アカウント作成の目的
担当者
メール
必要書類を提出
以下の必要書類(PDF)をアップして、法人KYCの手順は完了となります。
必要書類
法人設立証明書(登記簿謄本)
定款
最新の株主名簿
最新の役員名簿
企業利益の25%以上を保有する最終受益者の情報
会社の全役員情報(氏名、国籍、本人確認書類)
会社の組織図
KYCの承認は、通常3〜5営業日程度で完了します。審査が通過すれば、KYC認証が完了となり、法人としての取引が可能となります。
他社(Bitget/MEXCなど)との比較
Bybit以外にも、法人口座を開設できる海外仮想通貨取引所は存在します。中でも、日本人ユーザーが多く、同様に法人KYCに対応しているBitgetとMEXCは有力な選択肢となるでしょう。自社にとって最適な取引所を選ぶためには、手続きの難易度やサポート体制などを比較検討することが重要です。
ここでは、主要3社の特徴を一覧表にまとめました。
どの取引所を利用しても、法人化による節税効果そのものに違いはありません。これは日本の税法で定められているためです。したがって、選択のポイントは「手続きのしやすさ」と「サポート体制」、「税務申告のしやすさ」の3点に集約されます。
Bybitは必要書類が比較的シンプルで、標準的な手続きを好む法人に向いています。一方、BitgetやMEXCは24時間体制の日本語サポートを提供しており、特にBitgetは法人口座向けの専属サポートも用意しているため、手厚い支援を重視するなら有力な候補となるでしょう。
税務申告の際には取引履歴の出力が必須となりますが、各社で出力できるデータの種類や形式が異なるため、自社の経理体制に合った取引所を選ぶ視点も重要です。
Bybit法人口座に関するよくある質問(FAQ)
ここまでBybitの法人口座について、その開設方法からメリット・デメリットまで詳しく解説してきました。しかし、実際に手続きを検討する段階では、まだ解決すべき細かな疑問点が残っているかもしれません。
ここでは、特に多くの人が抱くであろう質問と、それに対する明確な回答をQ&A形式で紹介していきます。個人口座との併用や、一人会社の開設可否など、具体的な疑問を解消し、安心して手続きに進めるようにしましょう。
個人口座と法人口座を両方持つことはできますか?
はい、個人口座と法人口座を両方持つことは可能です。ただし、それぞれ別々のアカウントとして開設する必要があります。
Bybitでは、1つのメールアドレスで登録できるアカウントは1つだけというルールがあるためです。したがって、個人用のメールアドレスで登録したアカウントで個人KYCを完了させ、それとは別に、法人用のメールアドレスで登録したアカウントで法人KYCを申請・承認されることで、実質的に両方の口座を保有し、使い分けることが可能となります。
1つのアカウントで個人と法人のステータスを同時に持つことはできない点に注意が必要だです。
一人会社や設立直後の法人でも開設できますか?
はい、一人会社(マイクロ法人)や、設立して間もない法人でもBybitの法人口座を開設することは可能です。
Bybitの審査では、会社の規模や事業年数そのものは問われません。最も重要なのは、法務局への法人登記が正式に完了しており、法人KYCで求められる登記簿謄本や定款といった必要書類一式を、不備なく提出できることです。
これらの条件さえ満たしていれば、会社の形態や設立からの期間に関わらず、問題なく口座開設を申請できます。
法人口座の開設に費用はかかりますか?
Bybitで法人口座を開設する際、取引所自体に支払う手数料は一切ありません。口座の開設や維持に関する費用は無料です。
ただし、これはあくまでBybitでの手続きに限った話です。法人口座開設の前提となる「法人設立」と、法人KYCで求められる「必要書類の取得」には、当然ながら別途コストがかかります。具体的には、法人登記にかかる登録免許税や、法務局で登記簿謄本を取得する際の手数料などがこれに該当します。
口座開設は無料ですが、法人化そのものには費用がかかるという点を理解しておく必要があるでしょう。
まとめ:Bybit法人口座は節税メリット大!計画的な準備で開設しよう
本記事では、Bybitの法人口座開設方法から、個人口座との違い、税務上のメリット・デメリットまでを網羅的に解説しました。
法人化には、設立や維持のコスト、資産の流動性低下といった注意点も存在します。しかし、個人の高い税率を大幅に軽減できる可能性や、損益通算・繰越控除といった制度を活用できるメリットは非常に大きいです。
仮想通貨取引で継続的に利益を上げている投資家にとって、法人口座の開設は手間をかける価値のある選択肢と言えるでしょう。まずはこの記事を参考に、計画的な準備を始めてみてください。
【免責事項】 本記事はPR記事であり、コインテレグラフジャパンは当ページのいかなるコンテンツ・製品・商品・暗号資産も推奨していません。読者は当記事で言及される企業・サービス及び仮想通貨に関係した如何なる行動をとる前に、独自の調査を行い判断する必要があります。また当記事は投資の助言・アドバイス・推奨ではありません。